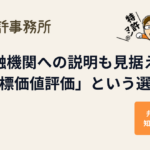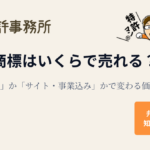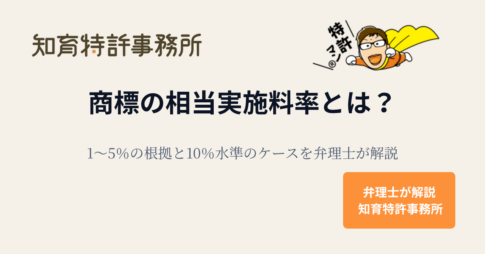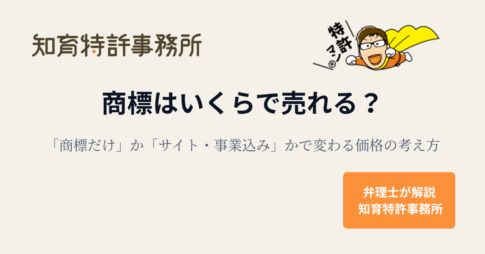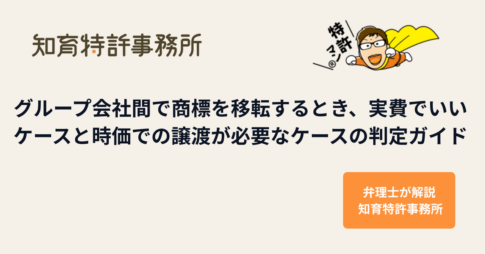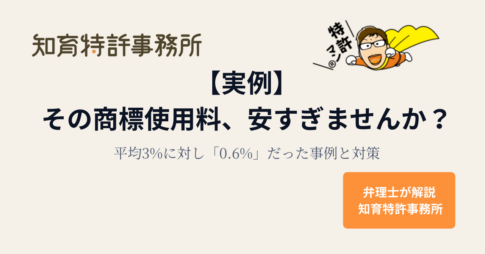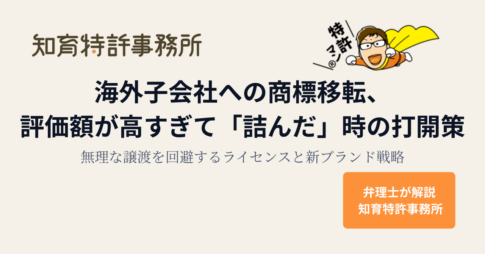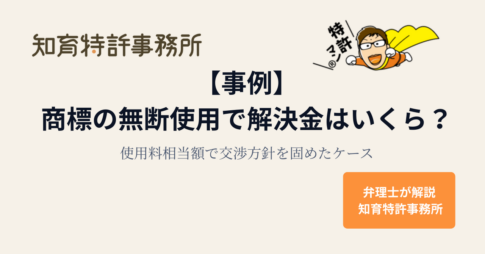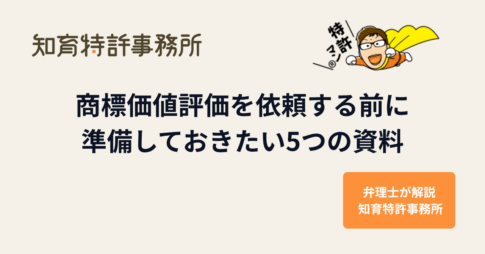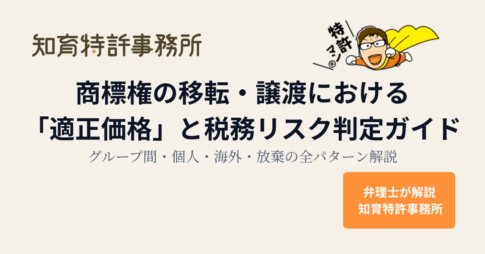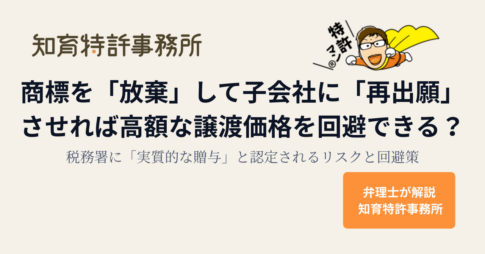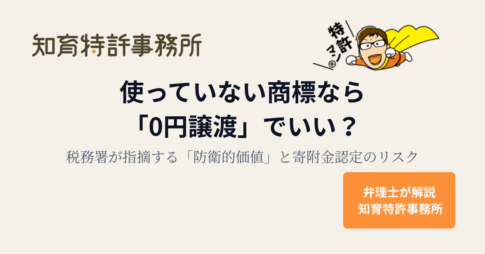事業で使っている商品名・サービス名・ロゴなどの商標(登録済み・出願中)は、日々の売上に直結していても、「どのくらいの価値があるのか」は数字として見えづらいものです。
一方で、譲渡・グループ内移転・協業・更新可否の判断などの場面では、「この商標はどのくらいの金額で扱うべきか」という目安が、できれば短期間で必要になることがあります。
この記事では、そうした場面を想定し、RFR法にもとづいて最短7日程度で商標価値の目安を出す簡易評価の考え方と実務の進め方をまとめます。計算手順の全体像は総合ガイド👉 商標価値の出し方(簡易RFR)に整理しており、本記事では「短期間で数字を出す」という観点に絞って解説します。
1. 評価の対象になる商標(商品名・サービス名・ロゴ)
まずは、どのような商標(商品名・サービス名・ロゴ)がこの簡易価値評価の対象になるのかを整理します。代表的には、次のようなケースです。
- 登録済みの商標(商品名・サービス名・ロゴなど)
- 出願中の商標(登録を前提に使い始めている名称)
- すでに実務で使っているブランド名やシリーズ名で、今後の商標登録を検討しているもの
※ 未登録の名前だけでも整理は可能ですが、その場合は、「将来の商標取得を前提にした参考値」としての位置づけになります。実務上は、登録済み・出願中の商標の方が、価値の根拠を整理しやすくなります。
2. なぜ短期間で数字が出せるのか(RFR法の考え方)
当事務所では、商標・ブランド価値の算定で広く使われるRFR法(Relief from Royalty:ロイヤリティ免除法)の考え方をベースにしています。
RFR法とは?「その商標・ブランドを他社から借りるとしたら、売上の何%を支払うか」という発想で、事業に対する貢献度を金額に置き換える方法です。
より詳しい仕組みは、こちらの解説ページで説明しています:👉 RFR法の基本ガイド
RFR法で商標の価値を算出するための手順はシンプルで、次の流れになります。
- 相当実施料率(その商標を他社から借りるとしたら、売上の何%(例:1〜5%)を使用料として支払うか)を決める
- 売上×相当実施料率=その商標が「1年間に生み出す価値の目安」を計算する
- 商標を使い続ける期間(例:2〜3年)を想定し、その間に商標が生み出す価値を合計する
- お金の時間価値を反映し、先の年ほど価値を少し割り引き、今の時点の金額(現在価値)に換算する
- 条件の幅によるぶれ(売上や相当実施料率の増減)を踏まえ、商標の評価額の「上限〜下限のレンジ」を導く
この方式を使うことで、「最短5〜7営業日」でも、社内外で説明しやすいレベルの評価書を提示することができます。
3. こういうケースで役立ちます
- 商標を譲渡する際に、どの程度の金額で扱うべきか目安を整理しておきたいとき
- 関連会社・グループ内で、商標をどの会社に集約するか検討したいとき
- 協業・共同プロジェクトの検討で、その商標の使用料などを整理しておきたいとき
- 商標更新のタイミングで、「残す商標/手放す商標」を検討したいとき
- ブランド名やロゴをリニューアルする前に、現在の商標の価値を把握しておきたいとき
いずれも、「今すぐM&Aのために精緻な企業価値評価をする」というよりは、「商標の扱いを決めるための短期評価」として利用されるイメージです。
4. 評価内容(どんな資料が手に入るのか)
簡易価値評価では、商標の価値を「どのように判断したのか」「商標の価値が、どのくらいの金額帯になるのか」を、関係者が確認できるように資料として整理します。実務では、次のような形で提供されるケースが多いです。
- 1枚のサマリー(要点と商標の価値の金額帯を一覧化)
- 詳細な評価書(前提・試算・条件を変えた際の金額の変化)
「なぜこの金額帯になるのか」が説明できる構成になっており、社内稟議・取引先説明・比較検討などでそのまま使えます。
5. よくある質問(実務でよく聞かれるポイント)
商標の価値を整理する際に、実務でよくいただく質問を補足としてまとめました。検討時に知っておくと安心なポイントです。
Q. 機密情報は大丈夫?
弁理士には法律上の守秘義務がありますので、原則としてNDA(秘密保持契約)は不要です。ただし、貴社の社内規程などで締結が必要な場合は、NDAにも対応しています。
Q. どんな情報が必要?(概算でOK)
- 直近3〜6か月の売上・粗利
- 広告費・チャネルの比率
- 対象商標(または候補名)の登録/出願状況
Q. まだ登録していない名前の評価は?
出願前の名称についても整理は可能ですが、将来の商標取得を前提にした参考値としての扱いになります。収益ベースでの算定が難しい場合は、再取得コスト等を用いた参考評価にとどめることもあります。
6. まずは前提条件のすり合わせから(無料)
商標の価値を、短期間で整理してみませんか?
関連記事
商標価値評価(簡易RFR)に関する関連記事をまとめた一覧は、こちらの総合ページに整理しています:商標価値評価|RFR法の基礎と実務ガイド(まとめ)
次の一歩
- 商標価値の簡易評価サービス(簡易RFRレポート):自社ブランドの価値をざっくり数字で把握したい方向けのサービスです。
- 簡易RFRによる商標価値評価が事業判断の根拠になる理由:なぜこのRFR法が社内稟議や交渉で使えるのかという論理的根拠を深く知りたい方はこちらをご覧ください。
- 3Dプリント試作サービス:新しいブランドとあわせて製品の試作も進めたい場合はこちらをご覧ください。
- 無料相談(30分):どのサービスが自社に合うか分からない場合は、まずは無料相談で方向性を一緒に整理します。
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)