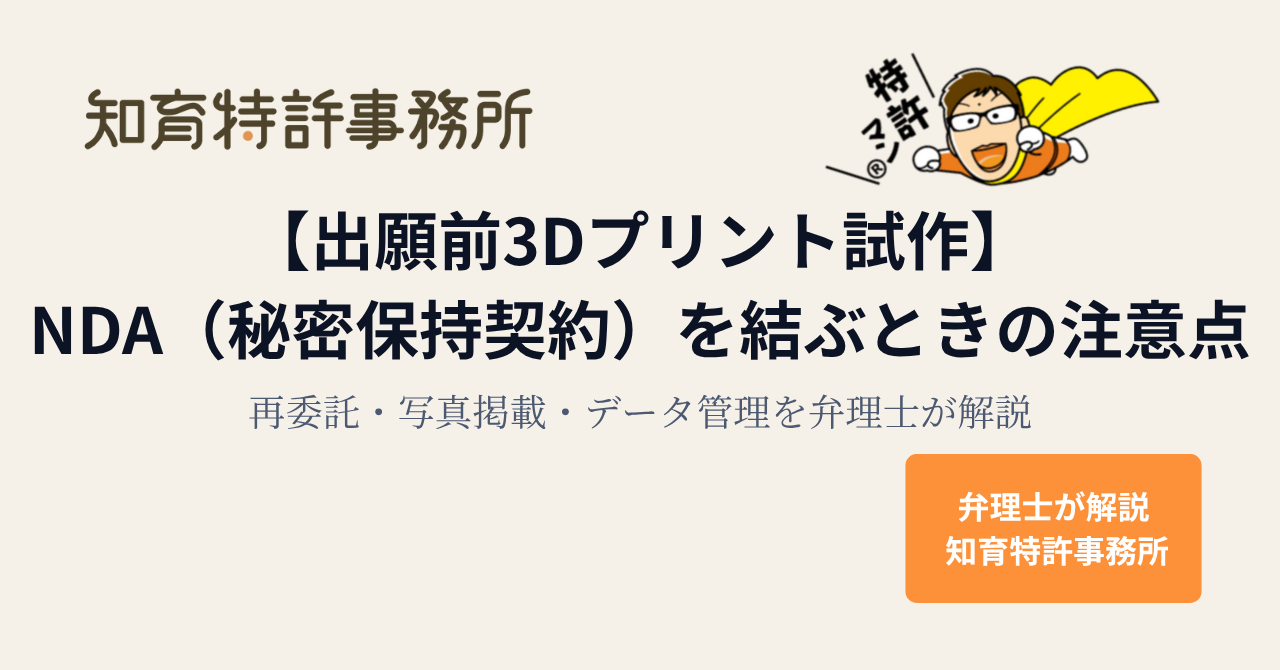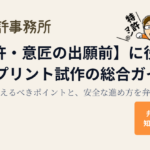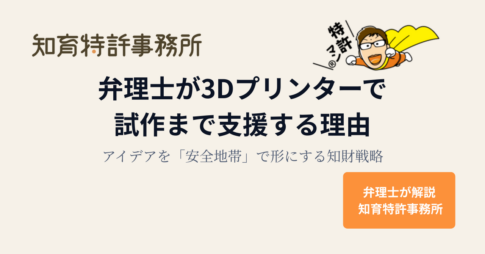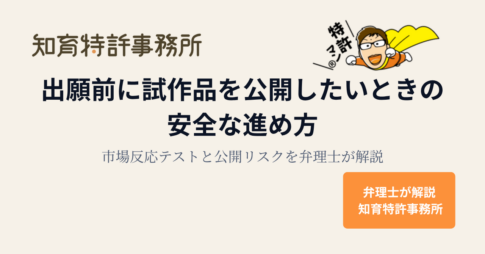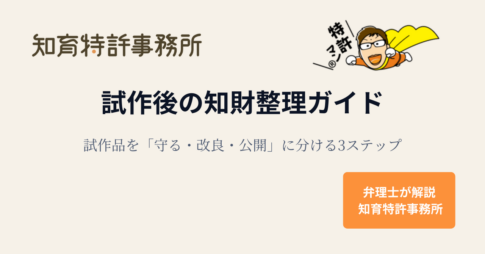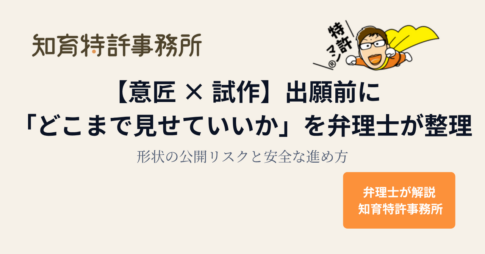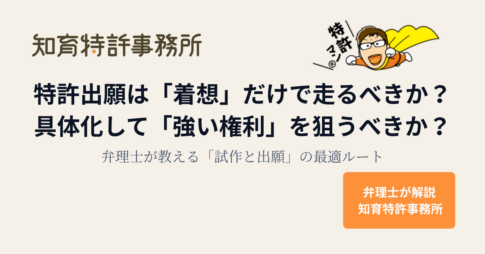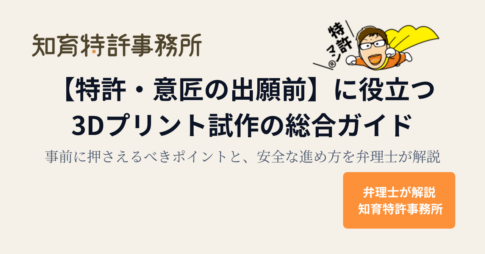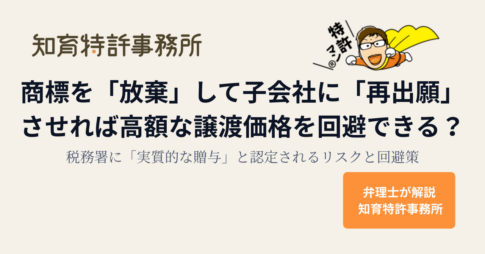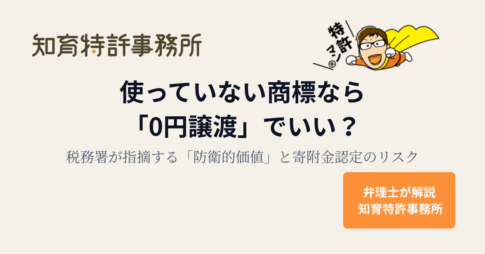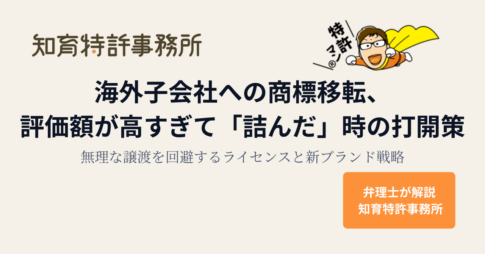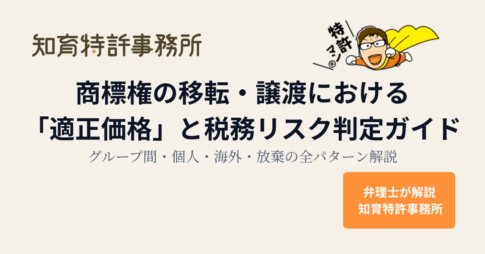製品づくりや新しいアイデアの検討では、社外の業者に試作を依頼するために、3Dデータ・図面・寸法情報などを外部に渡す場面があります。試作の方法は 3Dプリントに限らず、外観をざっくり形にする簡易モデルや、重要な部分だけ先に確かめる部分試作など、目的に応じてさまざまです。そして、この「試作のために社外へ情報を渡す」という場面で問題になるのが、
- どこまで情報を渡してよいのか
- 渡した情報が外でどう扱われるのか
という点です。
特に、特許や意匠の出願を視野に入れている場合、出願前の情報が意図しない形で外部に広がると新規性が失われたり、取得できた権利が後になって有効ではないと主張されるリスクが生じます。
そこで本記事では、外部に試作を依頼するときに最低限おさえておきたい NDA(秘密保持契約)のポイントを、弁理士の視点で分かりやすく整理します。
1. なぜ試作ではNDAが重要なのか
出願前の試作では、次のような情報が外部に渡る可能性があります。
- アイデアの核心となる構造
- 外観デザインの特徴
- 寸法・クリアランスなどの具体的な数値
- 材料や加工方法などの仕様
このような情報が意図せず広まると、
- 特許・意匠の新規性が失われる
- 取得した権利が後から「有効でない」と主張される
- 競合に製品構想のヒントを与えてしまう
といったリスクが生じます。そのため、試作会社に依頼する場合は、
- どの情報を渡すのか
- 渡した情報をどのように扱ってもらうのか
この2つを分けて整理しておくことが重要です。
2. NDAで特に確認すべき3つのポイント
NDAは「結んでおけば安心」というものではありません。試作会社の社内で情報がどう扱われるかは、依頼側からは完全に確認できないため、再委託・写真掲載・データの扱いなど「トラブルになりやすい部分」は、契約の条文で明確に定めておくこと が重要です。
2-1. 再委託(外部業者への依頼)の有無
試作会社が、試作品の加工や仕上げなどといった一部の工程を別の会社に任せるケース(再委託)があります。NDAに再委託が可能な条項があると、あなたのデータを別の会社が扱う可能性が生まれます。
確認したいポイント:
- 再委託が「原則禁止」かどうか
- やむを得ず再委託する場合は「事前に通知」があるか
再委託が完全NGでなくても、「提供したデータを扱う会社が知らないうちに増えていた」状況だけは避けるのが基本です。
2-2. 写真掲載・事例紹介の扱い
試作会社には、実績ページやSNSに製作した試作品を掲載する文化があるところもあります。これは出願前では絶対に避けたい公開リスクです。
確認したいポイント:
- 写真掲載は「禁止」が基本になっているか
- 例外的に掲載したい場合は「事前に許可を求める運用」になっているか
写真掲載については「原則禁止」とし、やむを得ない事情がある場合のみ、事前に相談してもらう形にしておくのが安全です。
2-3. データの保存期間・削除方法
試作が終わった後、提供したデータがどのように扱われるかも重要です。
確認したいポイント:
- データを保存する期間(必要最小限になっているか)
- 削除の方法(バックアップも含めて消去されるか)
- 削除が完了したことを通知する運用か
ここが曖昧なままだと、将来、想定外のルートで情報が外に出るリスクが残ります。
3. 実務上よくある「情報の渡し方」の工夫
NDAを結んだうえで、さらに実務上できる工夫があります。
- 試作に必要な最小限のデータだけを渡す
- 別案(改良案・比較案)は共有しない
- コンセプト資料・事業計画などは渡さない
- 意匠候補が複数ある場合は今回の案だけを出す
「全部渡す」のではなく、「今回の試作に必要な範囲だけを出す」 という考え方が、最も現実的で安全です。
4. 出願前の外部試作で押さえておきたい2つのポイント
出願前に外部に試作を依頼する場合の要点は、シンプルに次の2つです。
- 今回の試作に必要な情報だけ渡す
- 渡した情報が想定外に広がらないように管理する(再委託・掲載・データ管理など)
この2点を押さえておくことで、出願前の外部試作でも公開リスクを抑えた安全な運用が可能になります。
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 出願前に試作を外部に依頼する場合、NDAは必ず必要ですか?
はい。出願前の試作では、アイデアの核心部分やデザインの特徴が外部に伝わる場合があるため、原則としてNDAを結んでおくことをおすすめします。意図せず情報が広まると、新規性喪失や権利の有効性に影響するおそれがあります。
Q2. NDAで最も重要なポイントは何ですか?
特に重要なのは次の3点です:
・再委託の可否と条件
・試作物の写真掲載(事例紹介)の扱い
・データの保存期間・削除方法
これらを曖昧にすると、知らない会社にデータが渡ったり、出願前の公開につながるリスクがあります。
Q3. 試作会社が別の業者に再委託する場合はどうすればいいですか?
再委託を完全に禁止する必要まではありませんが、最低限、NDAの中で
- 再委託する場合は必ず事前に知らせてもらうこと
- 再委託先にも同じレベルの秘密保持義務を課すこと
- データを扱う会社が 「どこの会社なのかを全て把握できる状態」 にしておくこと
といった点を明確にしておくことが重要です。この3点がそろっていれば、「知らない会社にデータが渡っていた」という最悪のリスクを避けられます。
Q4. 試作データはどれくらいの期間保存してもらえばよいですか?
保存期間は必要最低限が基本です。長期間の保存は、将来の情報漏えいや運用ミスにつながるリスクがあります。試作完了後に削除する運用や、バックアップの取り扱い・削除完了の通知まで取り決めておくと安心です。
Q5. 最小限の情報だけ渡すというのは、具体的にどういうことですか?
試作に必要な部分(寸法・形状の一部・仕様の範囲など)だけを渡し、別案やコンセプト資料、複数のデザイン案は共有しないという考え方です。渡す情報を絞ることで、アイデア全体が外に拡散するリスクを減らせます。
6. まとめ:出願前の試作で必ず確認しておきたいポイント
NDAは「結べば安心」ではありません。具体的には次の項目を明確にしておく必要があります。
- 再委託の可否
- 写真掲載の扱い
- データの保存期間・削除方法
- 必要最小限の情報だけを渡す運用
これらを押さえておけば、出願前の試作で不必要な公開リスクを避けながら、安全に外部パートナーを活用できます。
📘 出願前の3Dプリント試作の「全体像」を整理した総合ガイド
出願前の3Dプリント試作の流れと、安全に進めるためのポイントは、
以下のページで体系的にまとめています。
次の一歩
- 3Dプリント試作サービス:触れる試作パック/知財戦略パックの内容や料金はこちらからご覧いただけます。
- 知財・試作・商標価値評価の総合ガイド:特許・意匠・商標との関係も含めて全体像を整理したい方はこちら。
- 無料相談(30分):試作の進め方や出願タイミングでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)