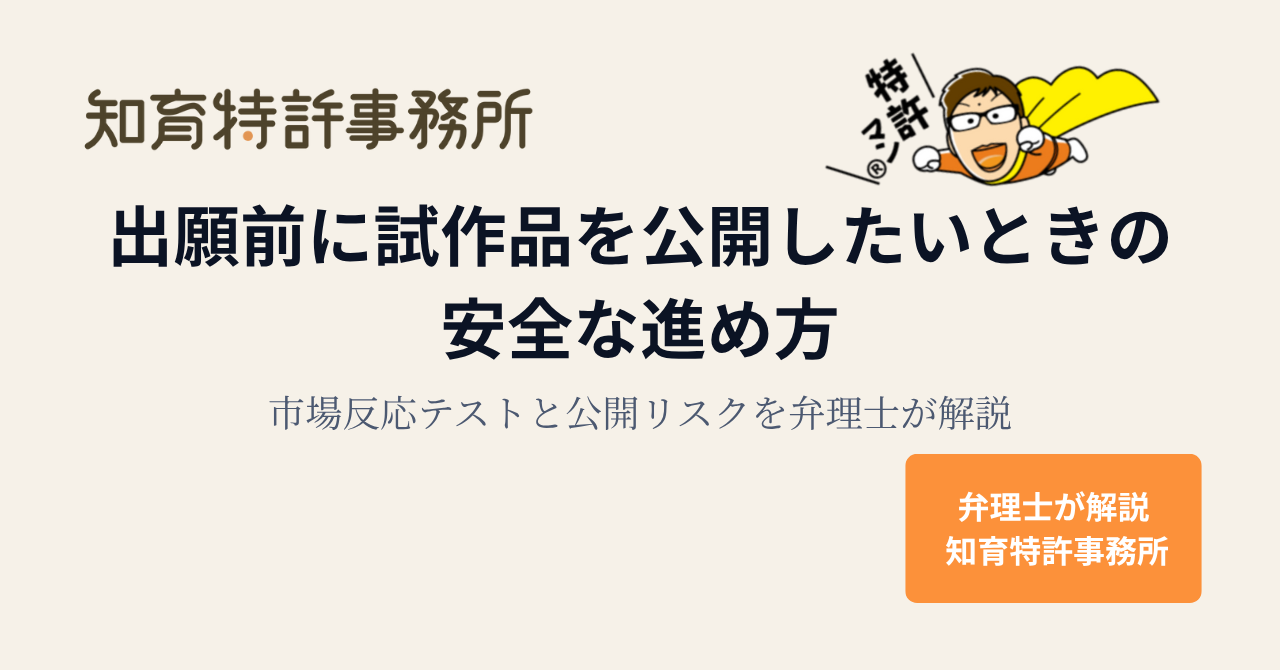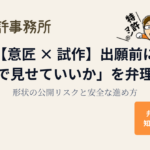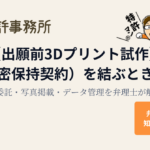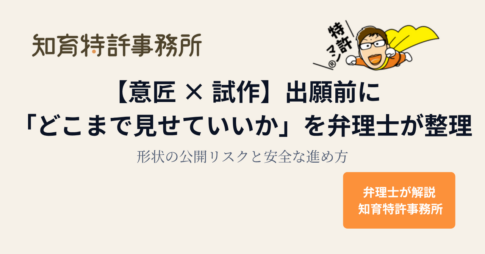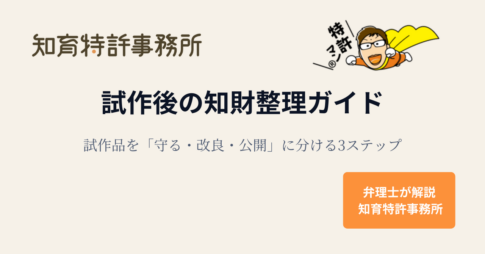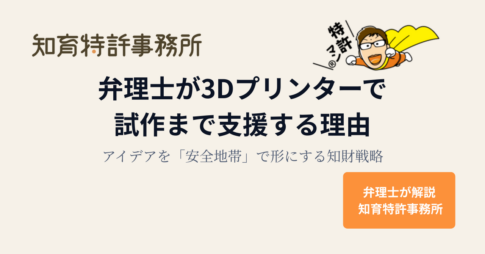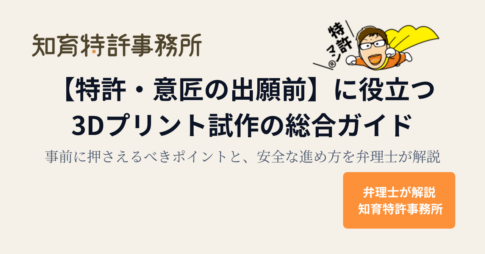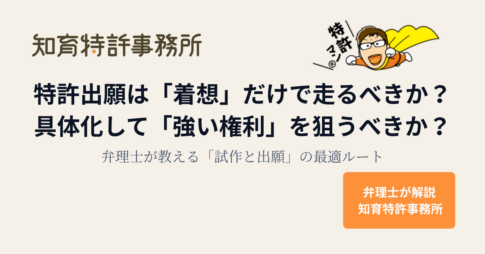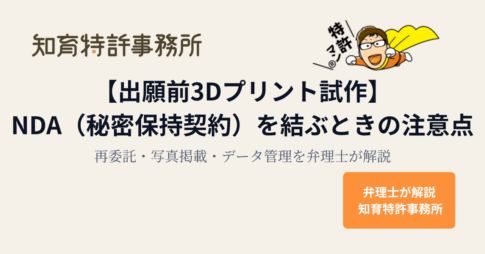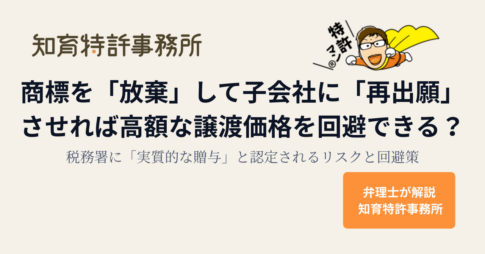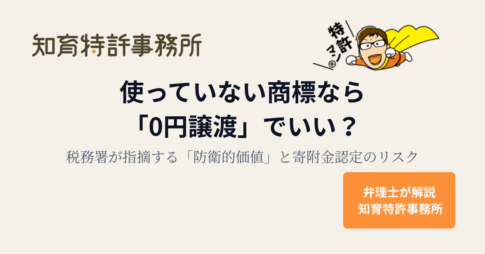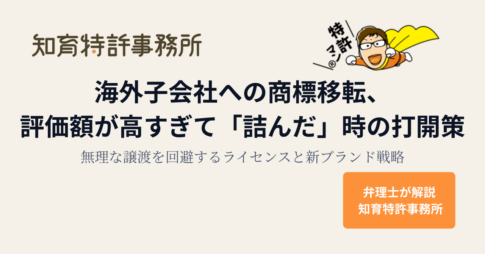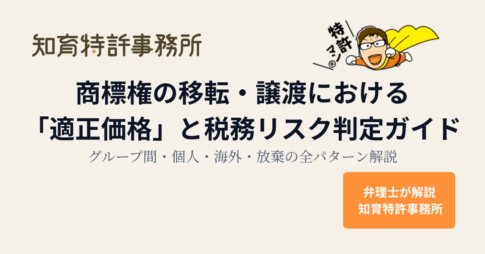製品のニーズを早めに把握したい、ユーザーの反応を見たい──そんな理由で、試作品の写真・イラスト・機能の一部を出願前に公開したいこともあります。
ただし、公開の仕方によっては、特許・意匠の新規性を失うおそれがあり、後から権利化しようとした際に不利になることもあります。
そこで本記事では、出願前に試作品を公開したい場合でも、「どこまでなら安全か」「どう見せると危険か」を中心に、リスクを抑える方法を弁理士の視点で分かりやすく整理します。
1. 出願前に公開したいときに必ず確認すべきこと
出願前でも「市場の反応を知りたい」「モニターに触ってもらいたい」という場面はあります。その際にまず整理しておくべき点は次の2つです。
- 何を公開するのか(公開範囲)
- 誰に公開するのか(公開先)
この2つの切り分けができると、どこにリスクがあるかが分かりやすくなります。
2. 公開前にできるだけリスクを下げる3つの方法
2-1. 公開前に「出願を先に済ませる」選択肢を検討する
最も安全なのは、試作品を公開する前に 特許や意匠を先に出願しておくこと です。出願は「完成してから」と思われがちですが、実務では 製品の要になるポイント が整理できていれば、完成前でも出願が可能です。
たとえば:
- 技術的な特徴となる中心的な仕組み・考え方(特許)
- デザインの印象を決める主要な部分(意匠)
といった「公開されると困る主要な部分」 が固まっている場合は、早めの出願が有効です。一方で、出願前にすでに公開されていた内容は、原則として特許・意匠の保護対象外になります。
なお、出願前に公開してしまった場合でも「新規性喪失の例外」という救済ルールに該当すれば保護が認められることもありますが、期間制限やリスクがあるため、通常は頼らない方が安全です。
2-2. モニター調査では必ず秘密保持の合意を取っておく
市場調査やモニター評価などで試作品を見せる場合は、NDA(秘密保持契約)や簡易な秘密保持合意を交わしておけば、試作品を見せても新規性を失わせる「公開」にはあたりません。特に、試作品を実際に見せたり触ってもらう場面では、
- 秘密を守れる相手に限定して試作品を見せること
- その相手と「試作品の情報を外部に出さない」ことを明確に合意しておくこと
この2点がそろっていれば、出願前でも安全に市場テストができます。
2-3. 公開する内容を「核心部分」と「周辺情報」に分ける
特許・意匠で保護したいのは、製品の“核心部分”です。具体的には、
- 新しい技術的なポイント(特許)
- 独自性をつくる形状・ラインなどのデザイン要素(意匠)
- 仕組みや工夫の本質が分かる部分
といった 「公開すると新規性に影響する可能性がある部分」 です。これらの核心部分は公開しないようにし、用途・サイズ感・色・利用シーン・雰囲気などの“周辺情報”だけを公開するという切り分けが重要です。核心部分を出さずに、周辺情報だけを出すことで、市場反応を得たい場合でも新規性への影響を最小限にできます。
3. どうしても公開したい場合の安全な見せ方
「核心は隠したいが、ある程度の公開は必要」という場合は、2-3 の原則を踏まえつつ、「見せ方」を工夫することでリスクを抑えられます。
3-1. 写真は「細部がわからない見せ方」にする
以下のように、特徴がわからない画像にする方法が有効です。
- 遠景で撮って細部を写さない
- 手や物で一部を隠す
- ぼかし・シルエット・暗部を使う
- 利用シーンだけを映し、製品本体は写さない
「特徴が読み取れない写真」にすることで、核心部分が露出せず、新規性への影響を抑えられます。
3-2. イラストは「抽象化して特徴を消す描き方」にする
イラストは安全そうに見えますが、細部を描くと公開と同じ扱いになります。次のように 意図的に特徴を消す描き方 がポイントです。
- 形状を簡略化して特定できないようにする
- 線を減らし、曖昧にする
- 構造や工夫が伝わる線は描かない
- シルエット・抽象化イラストにする
「アイデアの本質が読み取れない」ことが最優先 です。
4. すでに公開してしまった場合の対処方法
出願前に試作品を公開してしまった場合でも、特許・意匠ともに、まだ取れる手段があります。ただし、対応には「2つの観点」を分けて考える必要があります。
4-1. 自分の公開が原因で新規性を失うリスクへの対応
まずは、試作品を公開してしまった状況を整理します。
- どこで公開したのか(SNS/展示会/HP など)
- 誰が見た可能性があるのか
- どの程度の範囲で広まったか
自分や関係者の行為で試作品を公開してしまった場合でも、「新規性喪失の例外」 という救済ルールに該当すれば、公開された試作品について特許・意匠の取得が認められる場合があります。ただし、新規性喪失の例外の救済ルールには、
- 期間制限がある
- 証明資料が必要
- 万能ではない
といった制約があるため、早い段階での検討が必須です。
4-2. 公開した情報を競合に先に出願されるリスクへの対応
公開された試作品に関する情報を競合他社などが目にする場合もあります。そのため、競合が公開された試作品をもとに、あなたより先に特許や意匠を出願してくる可能性があります。これは「新規性喪失の例外」では救えません。このリスクを避けるために、新規性喪失の例外を利用してできるだけ早めに出願して、権利の「先取り」をしておくことが重要です。
4-3. まとめ
出願前に試作品を公開してしまった場合でも、特許・意匠の取得が可能なケースもあります。そのために、次の 2点をまずは検討すること が大切です。
- 自分の公開による新規性喪失への対応 → 「新規性喪失の例外」が使えるかを早めに検討
- 競合が先に出願してくるリスクへの対応 → 新規性喪失の例外が使えるならば、早めに出願して「先願」を確保
試作品を公開した 内容・時期・相手 によっては、試作品を公開した後に出願しても 問題なく権利化できるケースも多くあります。まずは状況を整理し、可能ならば早めに手続きを進めることが安全です。
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 出願前に試作品を公開すると、新規性はすべて失われてしまいますか?
すべての場合で新規性が失われるわけではありませんが、公開の仕方によっては特許・意匠の新規性を失うおそれがあります。特に、新しい技術的なポイントやデザインの特徴など、核心部分が分かる形での公開はリスクが高くなります。一方、用途や雰囲気など周辺情報にとどめるなど、公開内容を工夫すれば新規性への影響を抑えられる場合もあります。
Q2. 出願前に公開してしまった場合でも、特許・意匠の取得は可能ですか?
自分や関係者の行為による公開であれば、特許法上の「新規性喪失の例外」に該当する場合に限り、特許・意匠の取得が認められることがあります。ただし、利用できる期間に制限があり、公開状況を証明する資料も必要になるため、早めに専門家へ相談することが重要です。
Q3. 市場反応を確かめるために試作品を見せたいのですが、安全なやり方はありますか?
モニター評価など、見せる相手が限られている場合には、NDA(秘密保持契約)や簡易な秘密保持合意を結び、秘密を守れる相手に限定して試作品を見せる方法が有効です。公開範囲をコントロールできていれば、新規性を失わせる「公開」とならないケースも多く、安全に市場反応を得やすくなります。
Q4. 写真やイラストであれば、出願前に公開しても問題ありませんか?
写真やイラストであっても、細部まで形状や仕組みが分かるように公開すると、新規性に影響するおそれがあります。遠景で撮って細部を写さない、シルエットやぼかしを使う、イラストを抽象化して特徴を消すなど、核心部分が読み取れない見せ方にすることが重要です。
6. まとめ:公開したい事情があっても「守るべき部分」は守る
市場の反応を知るために、出願前に公開したい場面はあります。ただし、
- 核心部分は見せない
- 見せる相手を限定する
- 公開する情報は抽象化・簡略化する
- 可能であれば出せる部分だけ先に出願しておく
この4つを押さえるだけでも、新規性を失うリスクを大きく下げることができます。
📘 出願前の3Dプリント試作の「全体像」を整理した総合ガイド
出願前の3Dプリント試作の流れと、安全に進めるためのポイントは、
以下のページで体系的にまとめています。
次の一歩
- 3Dプリント試作サービス:触れる試作パック/知財戦略パックの内容や料金はこちらからご覧いただけます。
- 知財・試作・商標価値評価の総合ガイド:特許・意匠・商標との関係も含めて全体像を整理したい方はこちら。
- 無料相談(30分):試作の進め方や出願タイミングでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)