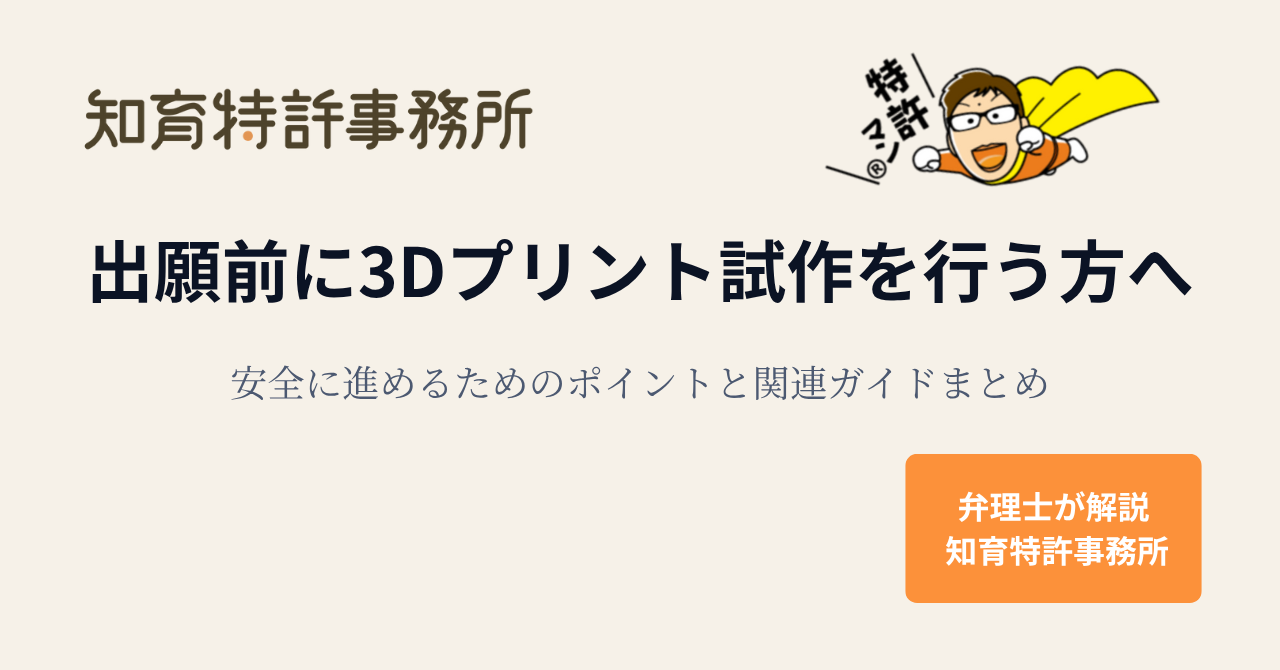製品開発の初期段階では、「まずは3Dプリントで形にして確かめたい」という場面があります。一方で、出願前の試作の進め方によっては、気付かないうちに特許や意匠の新規性が失われてしまうおそれもあります。
このページは、出願前の3Dプリント試作について、全体像 → NDA(秘密保持契約) → 公開リスク → 意匠の見せ方 → 特許の見せ方という流れで関連記事を整理した「まとめページ」です。
まず何から確認すべきか、どの記事を読めばよいかが一目で分かるよう構成しています。
1. 出願前3Dプリント試作の全体像を押さえる
出願前に3Dプリント試作を行う目的(技術の整理・見た目の確認・ブランド説明の準備)や、新規性・NDAなどの公開リスクにどう備えるかといった全体像を俯瞰したいときの総合ガイドです。
2. 外部試作にデータを渡すときの注意点(NDA・情報管理)
外部の試作会社に3Dデータ・図面・寸法・仕様などを渡すとき、再委託の扱い・写真掲載(実績紹介)・データ保存・削除方法など、NDAで抜けがちなポイントを整理したい方向けのパートです。
3. 出願前に試作品を公開したいときの注意点(新規性)
SNSや展示会などで市場の反応を得たいとき、
どこまで公開すると新規性に影響するかを整理したい方向けのパートです。
公開前に確認すべき「何を公開するか」「誰に見せるか」の切り分け、
安全な見せ方・危険な見せ方、すでに公開した場合の対応などを解説しています。
出願前に試作品を公開したいときの安全な進め方|市場反応テストと公開リスク
4. 意匠(デザイン)の観点から押さえるべき「見せ方」
試作品の写真や利用シーンを見せたいとき、形状の特徴が第三者にどこまで伝わると意匠の新規性に影響するかを確認したい方向けのパートです。安全な公開例・危険な公開例、部分意匠を使った出願の考え方などを整理しています。
【意匠 × 試作】出願前にどこまで見せていいか|形状の公開リスクと安全な進め方
5. 特許(技術)の観点から押さえるべき「見せ方」
構造・動作・仕組みといった技術的特徴が、試作品の公開でどこまで伝わると危険かを整理したい方向けです。技術の核心部分が読み取れる公開例、読み取れない公開例、完成前でも決まった部分だけ出願する戦略などを扱っています。
【特許 × 試作】出願前の試作品でどこまで技術を見せていいか
6. 出願前試作について関連記事をテーマ別に振り返る(まとめ)
ここまでの内容を、もう一度テーマ別に整理して俯瞰したい方向けのまとめです。出願前の3Dプリント試作を「どう活かすか」「どこに注意すべきか」を、理解できる構成にしています。
- 【特許・意匠の出願前】に役立つ3Dプリント試作の総合ガイド
└ 試作の役割(気付き・改良点の抽出・見せ方の判断)から、新規性・NDA・公開リスクの全体像までを体系的に把握できます。「まず全体を掴みたい」「どの順番で進めればいいか知りたい」方向け。 - 出願前試作のNDAで必ず確認しておきたいポイント
└ 試作会社に3Dデータを渡すときの契約面の抜けやすいポイント(再委託・写真掲載・データ削除)を、実務に沿って解説。外部依頼を安全に進めたい場合に「どこを止めておけば事故にならないか」が分かります。 - 出願前に試作品を公開したいときの安全な進め方
└ 市場反応テスト・SNS・展示会で公開したい時に、どこまで公開すると新規性に影響するかを体系的に整理。公開範囲/公開先の切り分け、核心部分と周辺情報の線引き、安全な見せ方・危険な見せ方が分かります。 - 【意匠 × 試作】出願前にどこまで見せていいか(形状の公開リスク)
└ 意匠として守るべき「特徴的な見た目」を、試作段階でどう判断するかを整理した記事。外観のどの部分が“特徴”として評価されるか、安全な写真の撮り方・危険な公開例まで一気に把握できます。 - 【特許 × 試作】出願前の試作品でどこまで技術を見せていいか
└ 構造・動作・仕組みといった技術的核心部分を出しすぎないための判断基準を解説したパート。技術部分の公開リスク、危険な見せ方、安全な公開、先に「決まっている部分だけ出願」する戦略も整理できます。
この5本を順番に読むことで、出願前の試作を「安全に」かつ「価値ある整理作業」として最大活用するための全体像を確認できます。
7. 出願前試作について個別に相談したい方へ(サービス案内)
出願前の3Dプリント試作は、早い段階での気付きと 新規性への配慮の両方を踏まえて進める必要があるため、 「どの順番で進めるのが良いか」「外部に依頼する際は何を注意すべきか」を 事前に整理しておくことが大切です。
知育特許事務所では、出願前の試作を次のような体制でサポートしています。
- 弁理士の法律上の守秘義務のもと、いただいたデータを外部に出さず安全に管理
- 必要に応じて NDA(秘密保持契約)の締結が可能
- 事務所内の3Dプリンタで完結するため、外部業者にデータを渡さなくても試作が可能
- 試作 → 公開範囲の判断 → 特許・意匠の出願内容の検討まで一貫して支援
- すでに公開してしまった場合の「新規性喪失の例外」利用可否の整理にも対応
「安全に試作を進めたい」「出願までの流れを一度まとめて確認したい」
という場合は、試作サービスまたは無料相談をご利用ください。
🧭 このページは、出願前の3Dプリント試作に関する「全体のまとめ(総合ガイド)」です。
出願前の3Dプリント試作を、安全かつ効果的に進めるための全体像を整理しています。
実務でつまずきやすい4つのテーマは、下記の記事で詳しく解説しています。
-
試作を外注するときの注意点(NDA:秘密保持契約)
外部業者に試作を依頼する際に「どこまで見せて良いか」「NDAで不足しがちな点」を整理。 -
試作品の公開で失敗しないために(新規性の注意点)
SNS・展示会・クラファンなどで公開したときの「新規性喪失リスク」を具体例で解説。 -
意匠として守りたい「特徴的な見た目」の見極め方
意匠として保護すべき「特徴的な見た目」を試作でどう確認するか、公開前の注意点と合わせて説明。 -
特許として守りたい「技術部分」の扱い方
特許で守りたい「技術的なポイント」を、試作段階でどこまで見せると危険か──新規性を失わないための注意点を整理。
この記事は、特許・意匠・商標の出願を検討している方に向けて、「出願前に3Dプリント試作を行うことで、どんな“気付き”や改良点が得られ、それを後の特許・意匠・ブランドづくりにどう活かせるのか」と、「出願前の3Dプリント試作を安全に進めるためのポイント」を整理した総合ガイドです。
3Dプリントで一度かたちにしておくと、図面やラフだけでは気づきにくい「重要なポイント」を早い段階で把握しやすくなり、後の特許・意匠の検討、製品説明やブランドづくりにも活かせる場面があります。
一方で、出願前に試作をすると、思わぬところで試作品が公開されてしまい、特許や意匠が取得しづらくなったり、後に無効を主張されやすくなるケースもあるため、「どこまで見せてよいのか」「どのように進めるべきか」を知っておくことが大切です。
この記事では、3Dプリント試作を「出願前の整理作業」としてどう活用し、どんな点に注意すれば安全に進められるのかを、弁理士の視点で分かりやすくまとめています。
1. このガイドで扱う「出願前の3Dプリント試作」とは
ここで想定しているのは、たとえば次のような段階の試作です。
- 図面や3Dデータのラフはあるが、まだ最終形は固まりきっていない
- まずは形や構造のイメージを確認したい
- まだ金型や量産設備には進んでいない
いわゆる「完成品に近い試作品」だけでなく、
- 外観だけをざっくり立体にして、イメージを確認したい
- アイデアを一度、立体として出してみて「どのようなものか」を確かめたい
といった、「出願前に一度かたちにしてみる」段階の3Dプリント試作を対象にしています。
2. 出願前に3Dプリント試作を行う主な目的
2-1. 特許的なポイントを早めに整理する
出願前に試作しておくと、特に次のような点がはっきりしてきます。
- どこに技術的な工夫がありそうか
- 従来品と比べて、どこが違っているのか
- 想定している「効果」が実際に出ていそうか
- どのような使い方で問題が出やすいか
3Dプリントは量産品と比べると強度・精度は劣りますが、
- 組み付けが思ったより難しい箇所がある
- ある使い方をするとガタつきや干渉が出やすい部分が見えてくる
- 力をかけたときに、想定していた場所とは別の部分に負担が集中していそうに見える
- 想定した効果が、イメージしていたほどは出ていない
といった「違和感」がわかることがあります。
これらは、
- どの部分に本当の独自性・工夫がありそうか
- どこを直せば、より良い製品になりそうか
を考える材料になり、改良すべき点や工夫として活かせそうな部分が見えてくるため、より良い製品づくりや、後の特許でポイントとなりそうな箇所を整理するヒントになります。
2-2. 意匠の「見え方・らしさ」をつかみやすくする
PC上の3Dデータや2D図面だけでは、どうしても「平面的な見え方」に偏りがちです。
実際に3Dプリントして机の上に置いてみると、
- どの方向から見たときの印象が一番その製品らしく見えるか
- どの部分が目立ち、どの部分はあまり見えないのか
- 既存製品と並べたとき、どこが違って見えるか/似て見えてしまうか
といった「立体としての見え方」が具体的になります。
意匠では、「どの方向から見た姿を中心に守るか」が非常に重要です。
試作によって、
- 正面からの見え方を重視すべきか
- 斜め上からの見え方を重視すべきか
といった、「どの見せ方を守るか」を判断する材料を得ることができます。
試作は、「どの見せ方を守りたいか」を決めるための材料になる、という位置づけです。
2-3. 製品説明・ブランドづくりの整理に役立つこともある
試作を重ねていくと、
- なぜこの形に落ち着いたのか
- 想定ユーザーはどう使う前提なのか
- 他の案ではなく、この案を採用した理由は何か
といったことを、開発メンバー同士で言語化する機会が増えます。
その結果として、
- 製品紹介ページやカタログで「この形にした理由」を説明しやすくなる
- 商品名やブランド名を考えるときのキーワードのヒントが出てくる
といった形で、出願だけでなく 製品説明やブランドづくりの整理 にもつながる場面があります。
(もちろん、最初にコンセプトがしっかりあり、その後で試作するケースも多く、試作だけですべてが決まるわけではありません。)
2-4. 出願前に向いている3Dプリント試作のタイプ
出願前の確認用として、3Dプリント試作が向いているのは、たとえば次のようなケースです。
- 外観をざっくり立体にして、全体イメージを確認したい場合
図面やラフだけでは掴みにくい「立体としての印象」を、早い段階で把握するためのもの。 - アイデアを一度かたちにして、「どのようなものか」を確かめたい場合
まだ最終形は固まっていないが、方向性の妥当性を見たい段階。 - 動作・干渉の「当たり」を確認したい場合
3Dプリントは量産品ほどの精度・強度はありませんが、「どこで干渉しやすいか」「どう動きそうか」といった「動作の方向性」を把握するには向いています。 - 外観+一部の重要構造だけを先に確認したい場合
全体モデルを作り込まず、今回の検証に必要な範囲に絞って立体化しておくことで、外観と構造の両方を早めに見ることができます。
いずれも「最終性能の評価」ではなく、出願前に「気付いておきたい部分」を洗い出すための試作という位置づけです。
3. 出願前試作で特に注意すべき「公開リスク」
3-1. 何が「公開」扱いになるのか
特許や意匠では、権利を取得するために「出願する前に、守りたいアイデアやデザインが世の中に知られていないこと」が大前提になります。
この「出願前に知られていない状態」 のことを、新規性と呼びます。
ついうっかり新規性が失われてしまう典型的な例としては、次のようなものがあります。
- 開発者自身が、試作品の特徴が分かる写真や動画をSNSに投稿してしまった
- 展示会で、試作品の構造や仕組みまで詳しく説明してしまった
- 守秘義務のない外注先が、自社サイトやSNSに試作品の写真を掲載してしまった
- クラウドファンディングのページで、完成形に近いデザインや機構を紹介してしまった
いずれも、「特許や意匠で守りたい部分が、出願前に公開された」と判断され得る行為です。
3-2. なぜ危険なのか(取れない・後で権利が揺らぐリスク)
このような形で公開されると、
- そもそも特許・意匠が取れなくなる
- 取得できたとしても、後から「その公開で新しさが無くなっていた」と指摘され、権利が揺らぐ
といった問題が出てきます。
社内の誰かや外注先が「少しだけ紹介したつもり」で写真や動画を出してしまうケースもあり、意図せず「自分たちで新規性をなくしてしまう」 パターンには注意が必要です。
ここで言う「権利が揺らぐ」とは、
後になって「その特許・意匠は権利として守られないはずだ」と主張され、争いの中で権利の有効性を問われ、場合によっては、その主張をきっかけに権利が消滅してしまうリスクが生じる、といったイメージです。
3-3. 「新規性喪失の例外」という救済と、その限界
日本には「新規性喪失の例外」という救済ルールがあり、一定の条件のもとで、公開後でも出願が認められる場合があります。ただし実務的には、次のような注意点があります。
- 公開から出願までの期間制限がある
- どこで何を公開したのかを、正確に特定した書面を提出する必要がある
- 後から「実はこの部分も公開されていた」と分かった場合、その部分については攻撃材料になり得る
そのため、「例外があるから大丈夫」と考えるのは危険で、できる限り 「例外を使わなくて済む進め方」 を取るのが現実的です。
4. 試作会社に依頼するときの「安全な見せ方・進め方」
4-1. 守秘義務とNDAは「最低限のスタートライン」
試作会社など外部に試作を依頼する場合は、まずは試作品を「見せてもよい相手」と「見せるべきではない相手」を分けておくことが重要です。
見せてもよい相手の例:
- 社内の開発メンバー(職務上アクセスが必要な範囲)
- 必要に応じて、守秘義務のある専門家(弁理士など)
- 守秘義務契約(NDA)を結んだ試作会社・外注先
見せるべきではない相手の例:
- 守秘義務のない知人
- SNSのフォロワー・展示会の一般来場者
- NDAなしの外注先
といった相手には、出願前の試作品は見せないのが基本です。
ここでNDA(秘密保持契約)は大事な前提ですが、「NDAさえあれば万全」というものではありません。契約の中身と、現場での運用の両方を確認しておくことが大切です。
4-2. NDAで特に確認しておきたい条項
たとえば次のような点は、NDAにおいて実務上よく検討が必要になります。
- 再委託の有無
さらに別の会社に再委託できることになっていないか。 - 紹介・掲載の扱い
作業事例として写真を載せてよいことになっていないか。 - データの保存期間と廃棄方法
試作後にどのようにデータを扱うか、定めがあるか。
契約書上は「秘密保持」となっていても、実際の運用がゆるいケースもあるため、可能であれば事前に「こういう形での紹介は控えてほしい」といった希望も伝えておくと安心です。
4-3. 「全部を出さない」情報の出し方
試作会社に渡すデータについては、「隠したい特徴は一切見せない」というよりも、「今回の試作に本当に必要な情報だけを渡す」という考え方が現実的です。
例としては:
- 今回検証したい案だけを渡し、将来検討したい別案までは共有しない
- 製品全体のコンセプトや事業計画など、設計に直接関係しない情報は渡さない
- 意匠候補が複数ある場合、今回は試作対象の案だけを出す
といった工夫があります。
「特徴そのものを隠す」のではなく、「その時点で不要な情報まで一緒に出さない」だけでも、外に出ていく情報量をかなり抑えることができます。
5. 試作で気づきやすくなるポイントと、その活かし方
5-1. 特許の視点で見たときの「気付き」
3Dプリント試作の段階で、
- 形状によっては、思ったより保持しにくい/持ちにくい
- ある使い方をするとガタつきや干渉が出やすい部分がある
- 想定した効果が十分に出ていない箇所がある
などが見えてくることがあります。
これらは、
- どの部分に改良すべき点があるか
- どの部分が工夫のポイントになりうるか
を考える材料になり、改良すべき点や工夫として活かせそうな部分が見えてくるため、より良い製品づくりや、特許出願の際に主張すべきポイントを整理するヒントになります。
5-2. 意匠の視点で見たときの「気付き」
意匠の観点では、次のような点が見えてきます。
- 実際に手に取ったとき、どの角度が一番その製品らしく見えるか
- 既存品と並べて置いたとき、どこが違って見えるか/似てしまうか
- 実際に使うとき、どの方向から見られる場面が多そうか
このような情報をもとに、「どの方向から見た形を中心に意匠で押さえるか」を決めていくイメージです。
試作は、「守るべき特徴的な見た目」を判断するための材料になる、という位置づけです。
5-3. 製品説明・ブランドづくりにどう活かすか
試作の過程で、
- 最終的にこの形が採用された理由
- 想定ユーザー・利用シーン
- 他案との比較で残ったポイント
を整理しておくと、
- 製品説明の文章(カタログ・LP)
- プレスリリースや開発ストーリー
- 商品名・ブランド名の候補出し
などに活用しやすくなります。
試作そのものがブランドを決めるわけではありませんが、「どういう考えでこの形にしたか」を説明しやすくする材料になるイメージです。
6. 試作 → 特許・意匠・商標へのつなげ方(全体の流れ)
出願前の試作を、弁理士視点でざっくり整理すると、次のような流れになります。
- アイデア整理(何を実現したいのか)
- 特許・意匠・商標・ノウハウなど、守り方の大まかな方針検討
- NDA・守秘義務など、見せてよい範囲の整理
- 3Dプリント試作(社内/外部)
- 試作結果からの「工夫点」「見せ方」の整理
- 特許・意匠の出願内容を決める
- 製品説明・ブランドづくりへ展開
この中で、試作は「単に形を作る作業」ではなく、試作の後のステップ──⑤の「工夫点」「見せ方」の整理、⑥の「特許・意匠の内容検討」、そして⑦の「製品説明・ブランドストーリーへの展開」──に必要な材料を集める工程という位置づけになります。
つまり試作は「出願のための材料集め」 と「伝え方の材料集め」 の両方に役立つもので、試作して終わりではなく、そこで得られた気付きや改良点をもとに、
- どこを技術的特徴として説明するか(特許)
- どの見せ方を中心に守るか(意匠)
- どのように製品の理由づけ・ストーリーを語るか(ブランド・PR)
を決めていく流れになります。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. すでに外注先に試作品を見せてしまいました。もう出願は遅いでしょうか?
ケースによって異なります。まず確認したいポイントは次の3つです。
- その外注先と守秘義務(NDA)があったかどうか
NDAがあると「公開扱いにならない」可能性は高まりますが、外注先が実績紹介として写真を載せてしまうケースもあるため、契約と実際の運用の両方を確認する必要があります。 - 試作品を外注先がどこまで共有した可能性があるか
(担当者のみが確認したのか、別部署に共有された可能性があるか、再委託が起きていないか、実績紹介として扱われていないか など) - 公開とみなされるような状態になっていないか
外注先内で広く共有されていたり、SNS・HPで誰でも見られる状態になっていた場合、「公開扱い」になる可能性が高まります。
NDAがある場合でも安心はできず、どこまで情報が広がっているかを確認することが重要です。
また、「新規性喪失の例外」を使える場合もありますが、期間や書面の要件があるため、早めに状況を整理することをおすすめします。
Q2. NDAを結べば安心して試作を任せて大丈夫ですか?
安心度は上がりますが、「NDAがあれば完全に安全」というわけではありません。
- 再委託の有無
- 紹介・掲載の扱い
- データの保存・削除ルール
など、契約書の中身と実際の運用をセットで確認しておくことをおすすめします。
Q3. 特許・意匠・商標はすべて取っておくべきでしょうか?
すべての案件で「特許・意匠・商標をフルセットにすべき」という話ではありません。
現実的には、
- その会社の現状や事業のステージ
- その案件にかけられる予算や人手
- 会社としての強み、この製品・サービスの位置づけや狙い
- どの程度まで模倣リスクを許容できるか
といった 経営的な観点も含めて考えることになります。
そのうえで、
- 「ここだけは最低限押さえておきたい」という部分について権利を取る
- 場合によっては、費用対効果を見てあえて権利取得を見送る
- 一部については、ノウハウとして社内管理にとどめる
といった判断になるケースもあります。案件ごとに、事業の目的に照らして何が現実的かを選んでいくイメージです。
知的財産権は「模倣品を完全になくす魔法の道具」ではありませんし、権利があっても模倣品の差止が難しい場面も多いのが正直なところです。
また、権利を取得したからといって、売上が上がるという性質のものではありません。
それでも、事業的・経営的に「ここは権利を取っておいた方が良い」と判断できるポイントについては、必要な範囲で備えておくという位置づけが現実的だと考えています。
Q4. クラウドファンディングで先に試作品を公開してしまいました。何かできることはありますか?
公開時期・公開内容などを整理したうえで、取れる選択肢が残っているかどうかを検討することになります。
特許・意匠・商標・不正競争防止法など、複数の観点から検討する余地があるため、まずは事実関係の整理から進めるのが一般的です。
8. 3Dプリント試作について弁理士に相談したい方へ
出願前の3Dプリント試作は、
- うまく使えば、出願内容の整理や説明に役立つステップになる一方で、
- 進め方を誤ると、新規性の喪失などにつながる繊細な場面でもあります。
知育特許事務所では、次のような体制で安全に試作を進められる環境をご用意しています。
- 弁理士の法律上の守秘義務のもと、いただいたデータを外部に出さずに管理
- 必要に応じてNDA(秘密保持契約)の締結が可能
- 外部の試作会社へデータを渡さず、事務所内の3Dプリンタで完結する試作
- 試作 → 出願内容の整理 → 製品説明・ブランドへの展開まで一貫したアドバイス
状況に応じて「どの進め方が安全で現実的か」を整理しながらご提案しています。
次の一歩
- 3Dプリント試作サービス:触れる試作パック/知財戦略パックの内容や料金はこちらからご覧いただけます。
- 知財・試作・商標価値評価の総合ガイド:特許・意匠・商標との関係も含めて全体像を整理したい方はこちら。
- 無料相談(15分/30分):試作の進め方や出願タイミングでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)