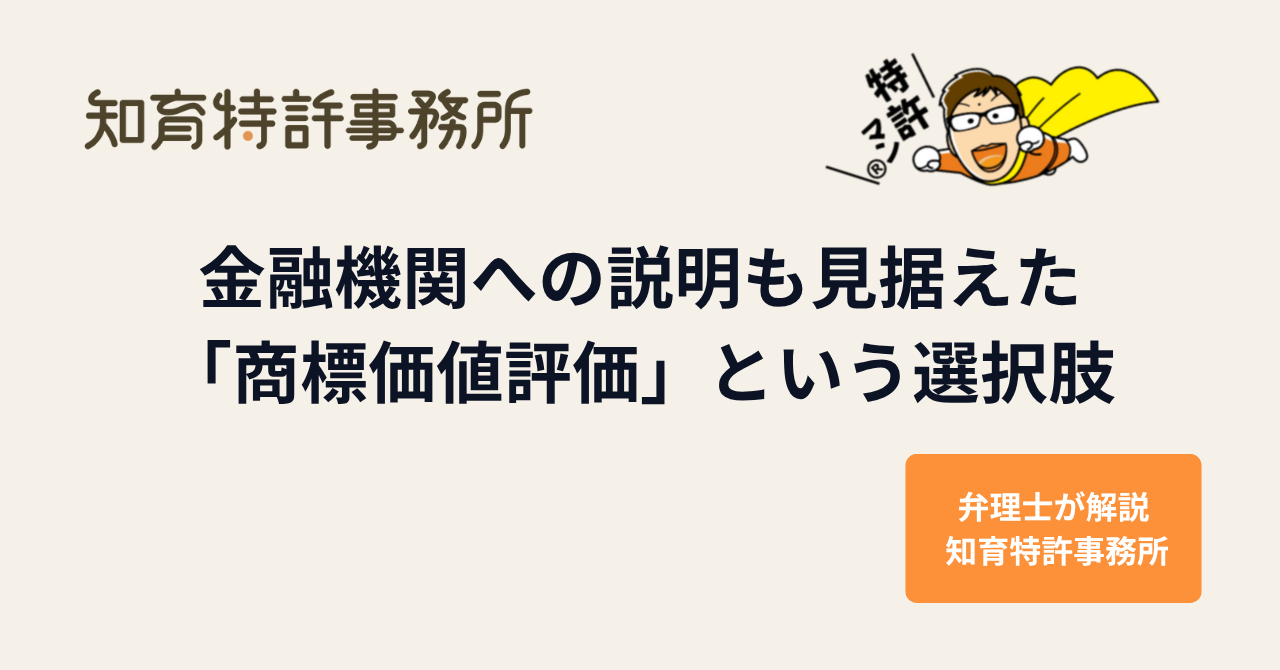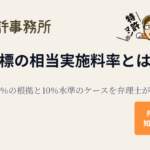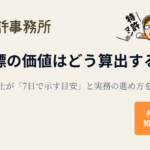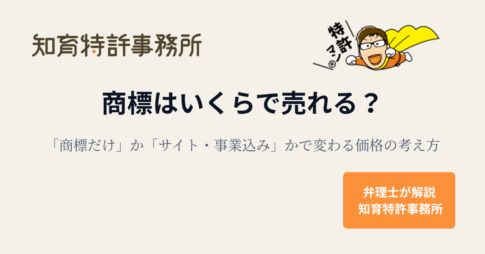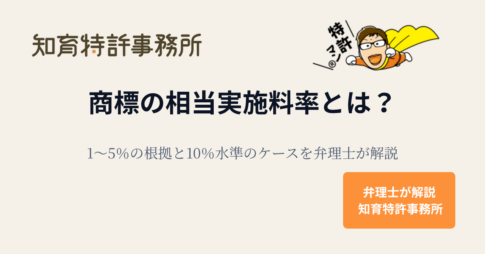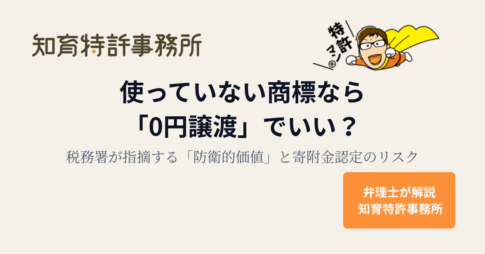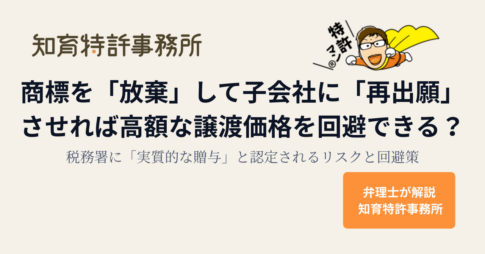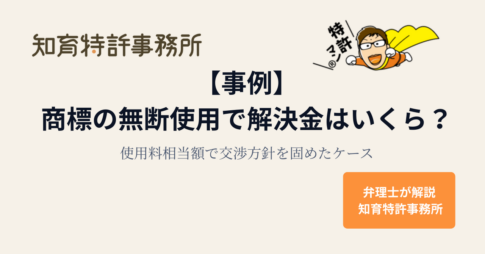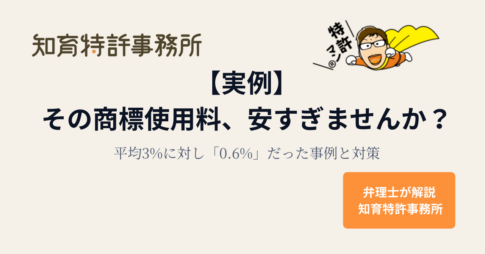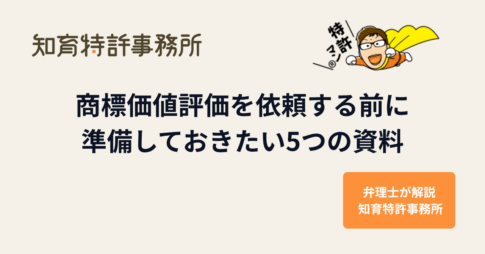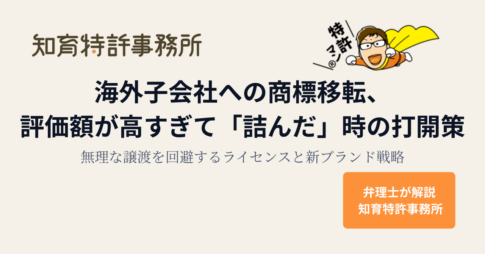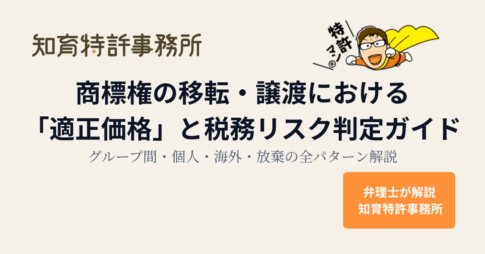金融機関との面談や融資審査の場面で、「うちのブランド(商標)が事業にどう効いているか」を、資料できちんと補足したい方向けの記事です。
商標価値評価そのものは融資の加点項目ではありませんが、事業内容やブランドの役割を整理して説明するための補足資料として活用できます。
本記事では、金融機関への説明も見据えて、商標価値評価をどう位置づけるかと、評価書の中で整理しておきたい基本的なポイントをまとめます。
商標の価値を具体的な金額に落とし込む流れやRFR法の基本的な考え方は、総合ガイド 👉 商標価値の出し方(簡易RFR)|稟議・融資・譲渡で使える基礎ガイドもあわせてご覧ください。
金融機関への説明も見据えた「商標価値評価」という選択肢
金融機関の融資審査は、基本的にはキャッシュフロー・担保・保証が中心です。商標の価値評価を行ったからといって、それ自体が融資審査の「加点」になるわけではありません。
一方で、商品名・サービス名などの商標が売上にどう効いているかを口頭だけで説明するのは難しい場面もあります。その補足として、必要に応じて商標価値評価の結果を資料として整理しておくという考え方があります。本記事では、その位置づけと整理の仕方をまとめます。
ポイント:商標価値評価は、融資の可否を左右するものではなく、事業内容やブランドの役割を伝えるための補足資料という立ち位置になります。
対象となる商標(商品名・サービス名・ロゴ)
ここで扱うのは、事業で実際に使われている商標です。具体的には次のようなものが対象になります。
- 登録済みの商標(商品名・サービス名・ロゴなど)
- 出願中の商標(登録を前提に使い始めている名称)
- すでに実務で使っているブランド名・シリーズ名で、今後の商標登録を検討しているもの
※未登録の名称だけでも評価は可能ですが、その場合は「将来の商標取得を前提にした参考値」としての扱いになりやすくなります。実務上は、登録済み・出願中の商標の方が、前提を整理しやすいのが実情です。
また、本記事は商標の価値評価に絞っており、意匠権や特許権などは対象外としています。
金融機関が知りたいポイント
金融機関は、商標そのものを担保として評価するわけではありませんが、事業内容を把握するうえで次のような点を確認したいことがあります。
- どの商標が、どの事業や商品・サービスに使われているのか
- その商標が、売上や顧客との関係にどのように貢献しているのか
- 今後もその商標を継続的に使っていく前提なのか(ブランド戦略)
- グループ内で商標を移転する場合、移転価格の考え方をどう整理しているのか
これらを口頭ベースだけで説明するのではなく、簡易な「商標価値評価」の資料として整理しておくことで、事業性評価(事業内容の理解)を補足しやすくなります。
商標価値評価で整理できる内容
商標価値評価そのものが融資の審査結果を直接変えるというよりも、次のような情報を整理しておくことで、金融機関との対話や事業計画の説明がしやすくなります。
- 対象商標の情報(登録状況・区分・使用範囲・使っている場面)
- 売上との結びつきを踏まえた、商標の役割の整理
- RFR法にもとづく商標の価値の目安
- 前提条件(売上・相当実施料率など)を変えた場合の金額の変化
ここでの評価は、厳密な鑑定というよりも、「ブランドの価値をお金(金額)で示す」ための簡易評価というイメージに近いものです。
なお、なぜこの評価が第三者に対する説明の場面で客観的な根拠となり得るのかという詳細な論理的理由は、👉 簡易RFRによる商標価値評価が事業判断の根拠になる理由 でもご確認いただけます。
RFR法の考え方(ざっくりとしたイメージ)
当事務所では、商標・ブランド価値の算定で広く用いられるRFR法(Relief from Royalty:ロイヤリティ免除法)の考え方をベースにしています。
RFR法とは?「この商標を他社から借りるとしたら、売上の何%を使用料として支払うか」という発想で、事業に対する貢献度を金額に置き換える方法です。手順をかみ砕くと、次のような流れになります。
- 相当実施料率を決める(その商標を借りるとしたら売上の何%を払うか/例:1〜5%)
- 売上 × 相当実施料率 = その商標が「1年間に生み出す価値の目安」を計算する
- 商標を使い続ける期間(例:2〜3年)を想定し、その期間に商標が生み出す価値を合計する
- お金の時間価値を考慮し、先の年ほど少し割り引いて、今の時点の金額(現在価値)に換算する
- 売上や料率の変動を踏まえ、商標の評価額の「上限と下限」を整理する
このように整理することで、「なぜこの価格帯になるのか」を、根拠をもって説明できるようになります。
なお、評価自体は最短5〜7営業日程度でドラフトを出すことが多く、第三者への説明資料や社内稟議の添付資料として使われます。
簡単な数値イメージ
イメージがしやすいように、ごく簡単な数値例を挙げます(あくまで仮の数字です)。
例:年商6,000万円/相当実施料率2.0%/期間2年の場合
- 1年あたりの価値の目安:6,000万円 × 2% = 120万円
- 2年間分を現在価値に換算した合計:およそ200万円前後
- 料率1.5〜2.5%など条件を振った場合のレンジ例:170〜280万円程度
実際の評価書では、こうした数字とあわせて、前提・計算方法などをまとめます。
評価書の構成と利用シーン
金融機関や社内での説明に使いやすいよう、評価書はおおむね次のような構成になります。
- 1枚の要約:対象商標、評価の目的、方法、商標の価格帯、留意点
- 詳細版:前提条件、試算表、前提を変えた場合の金額の変化など
これらを用いて、次のような場面で活用されることを想定しています。
- 事業計画書の「知的財産の活用」に関する説明を補足したいとき
- 金融機関との面談で、ブランドや商標の位置づけを説明する補足資料として使いたいとき
- グループ会社間で商標を移転する際に、社内の価格検討の材料としたいとき
繰り返しになりますが、商標価値評価そのものが融資審査の結果を直接変えるわけではありません。あくまで、事業の理解を助ける「説明用の土台」としてご利用いただくイメージです。
よくある質問
Q. 商標価値評価があれば融資が通りやすくなりますか?
審査の加点になるわけではありません。ただし、事業内容や商標の役割を説明する補足資料として、金融機関との対話をスムーズにする効果は期待できます。
また、「加点項目ではない一方で、なぜ説明責任に耐えうる資料として意味があるのか」という点については、👉 簡易RFRによる商標価値評価が事業判断の根拠になる理由 で、RFR法にもとづく評価の位置づけをより論理的に整理しています。
Q. 出願中の商標でも評価できますか?
可能です。「登録成立を前提とした簡易評価」など、前提条件を明記したうえで、やや保守的なレンジとして整理します。
Q. 守秘義務はどうなっていますか?
弁理士には法律上の守秘義務がありますので、通常は個別のNDAを結ばなくても対応可能です。貴社の社内規程でNDAが必要な場合には、締結にも対応しています。
サービス詳細・サンプル・相談窓口
商標価値評価のサービス概要やサンプル、事前相談の窓口は、次のページからご覧いただけます。
- サービス概要:商標価値評価サービスの詳細
- 評価書のイメージ:評価書サンプル(PDFプレビュー)
- 事前のオンライン相談(30分): 無料相談(30分)を予約する
「うちの事業で商標価値評価を使うとしたら、どこまで整理しておくと良さそうか」といった雑談レベルのご相談からでも大丈夫です。
商標価値評価の考え方そのものをもう少し詳しく知りたい場合は、商標価値の出し方(簡易RFR)|稟議・融資・譲渡で使える基礎ガイドもあわせてご参照ください。
関連記事
商標価値評価(簡易RFR)に関する関連記事をまとめた一覧は、こちらの総合ページに整理しています:👉商標価値評価|RFR法の基礎と実務ガイド(まとめ)
次の一歩
- 商標価値の簡易評価サービス(簡易RFRレポート):自社ブランドの価値をざっくり数字で把握したい方向けのサービスです。
- 簡易RFRによる商標価値評価が事業判断の根拠になる理由:なぜこのRFR法が社内稟議や交渉で使えるのかという論理的根拠を深く知りたい方はこちらをご覧ください。
- 3Dプリント試作サービス:新しいブランドとあわせて製品の試作も進めたい場合はこちらをご覧ください。
- 無料相談(30分):どのサービスが自社に合うか分からない場合は、まずは無料相談で方向性を一緒に整理します。
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)