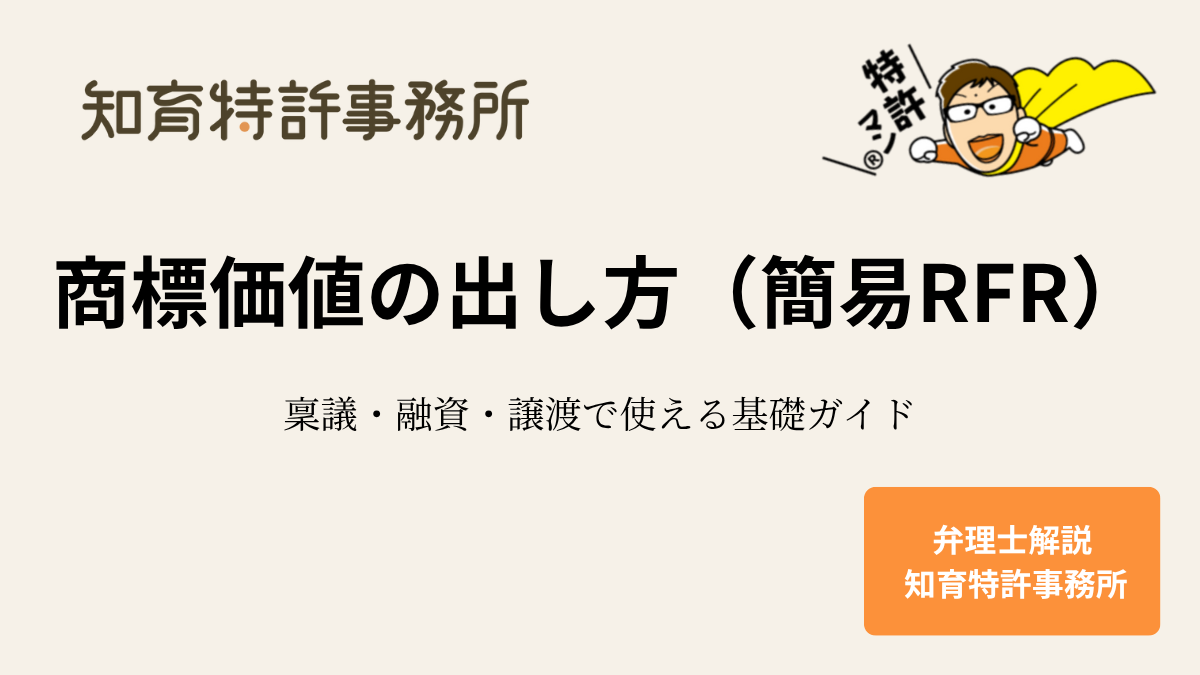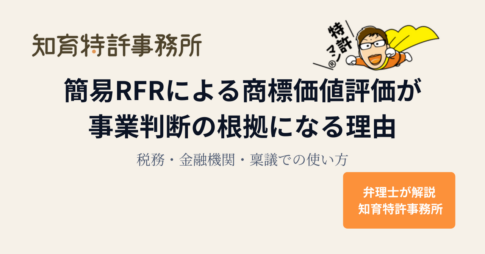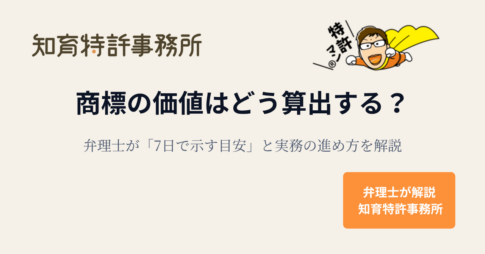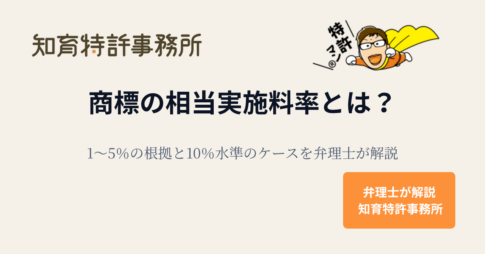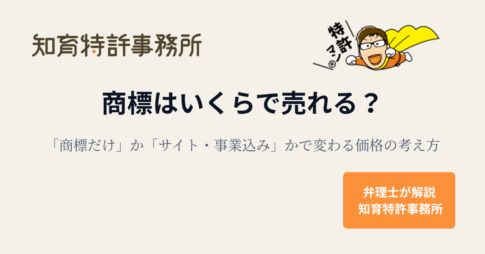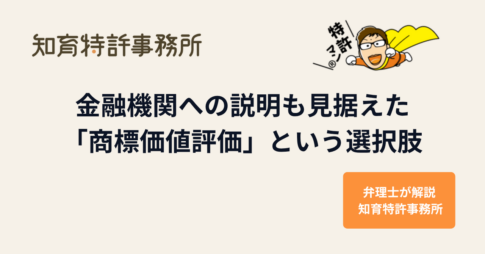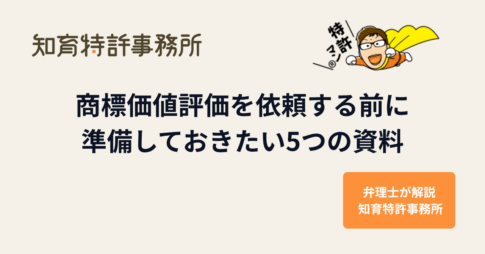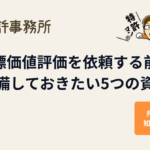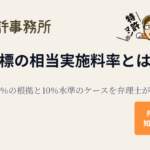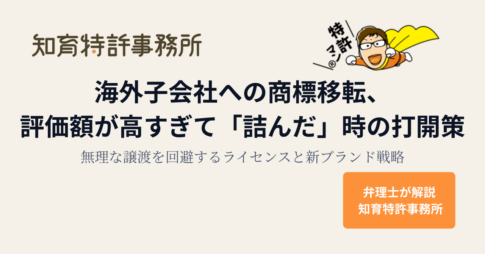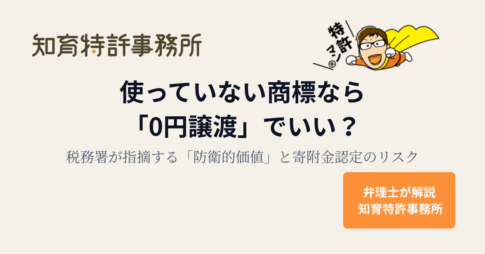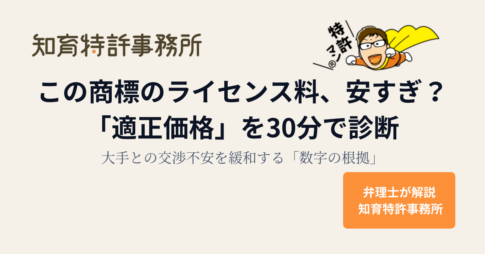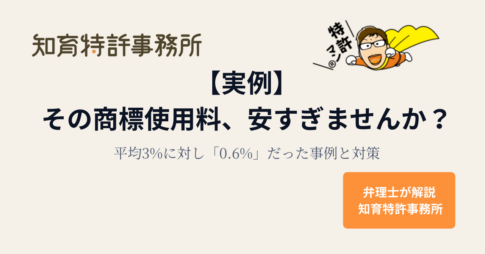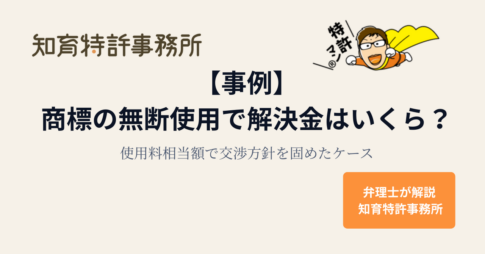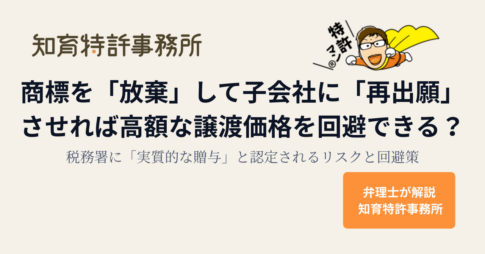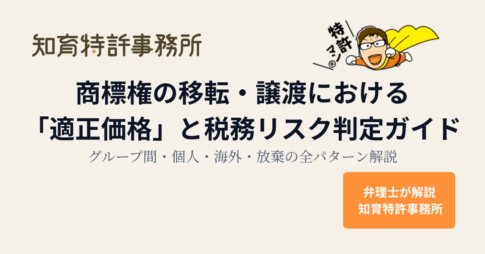商標の価値を社内や相手先に説明するとき、「根拠のある数字」をどう出すかを整理したい方向けの記事です。
本記事では、国際的に使われる RFR法(Relief from Royalty法)をベースに、短期間で商標価値の目安を出すための考え方と基本の流れをまとめました。
稟議・譲渡・金融機関への説明などで「この金額はなぜこうなったのか?」を伝えやすくするための、実務寄りの基礎ガイドです。
ロイヤルティ率(%)の決め方や譲渡価格の整理、短納期での進め方などの個別テーマは、相当実施料率(%)の考え方、譲渡価格の整理、短納期での進め方といった関連記事で詳しく解説しています。
1. RFR法とは? 基本の考え方
RFR法(Relief from Royalty法) は、商標やブランドが将来生み出す利益を、時間の経過を考慮して「いまの価値」に換算する考え方です。平たく言えば、そのブランドを持っていることで今後得られる見込みの利益を、いま基準の金額で見積る手法です。
RFR法の根っこにある発想が「Relief(免除)」です。 もし自社でブランドを保有していなければ、他社からブランドのライセンスを受けてロイヤルティ(商標使用料)を払い続けるはずです。自社でブランドを保有しているから、その支払いが免除されている——この「払わずに済むはずの使用料(みなしロイヤルティ)」を見積もり、いまの価値にそろえて合計したものが、ブランド(商標)の価値の目安になります。
なぜ「いまの金額」に換算するのか?
お金は受け取るタイミングで価値が変わります。将来の入金は計画どおりに入らないリスクもあり、確実ではありません。一方、いま手元にあるお金は、支払い・仕入れ・投資などにすぐ使える=自由度が高い。
そこでRFR法では、これから毎年(各年)見込まれる使用料額をリスクに合わせて少し「控えめ」に評価し、いまの金額にそろえてから合計します。 この「控えめにする度合い」を割引率と呼びます。
商標価値を出す基本の流れ
① ロイヤルティ率(%)を決める: 売上の何%をブランドのおかげ(使用料相当)とみなすかを決める(一般には1〜5%)。
② 各年の使用料額(円)を出す: 各年の見込み売上 × ロイヤルティ率=各年の使用料額。
③ 割引率で各年の使用料額を調整し、合計する:年が先になるほど調整幅を大きくして(=より控えめに評価して)「いまの金額」にそろえる。 そろえた各年の金額(調整後の使用料額)を合計すると、「いまの金額で見た商標の価値」(商標の現在価値)になります。
具体例
前提: 今後3年間、対象ブランドに紐づく売上1,000万円/年が継続。ロイヤルティ率3%(=使用料額30万円/年)、割引率10%と仮定。
割引率とは、お金を受け取るまで待つことによるリスクや機会損失を差し引くための係数です。お金を1年待つごとに1回この割引率の調整をかけるので、2年後なら2回、3年後なら3回と重ねて調整し、控えめに価値を見積ります。その結果、年が先になるほど「いまの価値」は小さくなります。
- 1年目の調整後の使用料額:30万円を1割控えめに → 約27万円
- 2年目の調整後の使用料額:30万円を1年目からさらに1割控えめに → 約25万円
- 3年目の調整後の使用料額:30万円を2年目からさらに1割控えめに → 約23万円
合計:27万+25万+23万 ≒ 75万円 → これが「いま時点の商標の価値(商標の現在価値)」の目安です。
背景や各論は次のコラムで詳しく解説しています:
2. いま数字を出すべき典型シーン
- 事業譲渡・商標譲渡する際に妥当な評価額の目安を素早く把握したいとき → 買い手・売り手の双方で根拠をもった交渉がしやすくなります。なお、グループ会社間や個人→法人での商標譲渡では、価格の決め方を誤ると寄附金課税などの税務リスクが発生する場合があります。パターン別のリスク判定は「商標権の移転・譲渡における「適正価格」と税務リスク判定ガイド」で整理しています。
- 社内稟議や意思決定の場面でブランド活用の判断を裏付けたいとき → 感覚的な議論に頼らず、根拠ある数字で投資判断やブランド方針を整理できます。
- 金融機関などに事業の中身を説明するとき → 商標が売上にどう関係しているかを補足する「説明資料の一部」として使われるケースがあります。※ 融資の可否そのものを左右する性質のものではありません。
3. 実務の進め方(最短5〜7営業日の流れ)
商標の価値を評価する流れは、次の4ステップで進みます。 初回ヒアリングからドラフト提示まで、最短で5〜7営業日ほどです。
- 前提の整理:対象商標(登録/出願番号・区分)、直近〜今後の売上概算、粗利、広告費、解約率・返金率などをヒアリングします(概算でOK)。具体的にどのような資料を用意しておくとスムーズかは、「商標価値評価を依頼する前に準備しておきたい5つの資料」でまとめています。
- 料率レンジの設計:業界相場と個別事情(周知性・独自性・販路・安定性など)を踏まえ、一般的には1〜5%前後を起点にしつつ、業種やブランド特性に応じて柔軟に設定します。
- 評価額の算出:各年の見込み額を、年数に応じて割り引いて「いまの価値」に換算し、複数のロイヤルティ率(料率)を適用した評価額をレンジ(※下記参照)で提示します。
- 1枚の要約に:目的・前提・計算方法・結果などを1ページに整理し、社内稟議や交渉資料としてそのまま使える形式に仕上げます。
ロイヤルティ率の考え方や短納期での進め方は、 料率の解説と 短納期ガイドで詳しく紹介しています。
なぜ評価額にレンジ(幅)をもたせて出すのか?
- ブランドの寄与度(=ロイヤルティ率)は商標の周知性・代替可能性・販路などで変動するため、評価額を単一値に固定すると「見せかけの金額」になりやすい。
- 意思決定(稟議・交渉)では標準/保守/楽観の複数シナリオが必要になる。
- ロイヤルティ率感度(±1%)を示すと、投資や条件変更の効き方(感度)が一目で伝わる。
例)年商1,000万円・割引率10%・3年の場合における評価額例
ロイヤルティ率2% ≒ 約497,000円/ロイヤルティ率3% ≒ 約746,000円/ロイヤルティ率4% ≒ 約995,000円
(同じ前提でもロイヤルティ率で評価額がこれだけ動く=感度が高い)
※ 評価書では、レンジ内の推奨値と推奨値の採用理由も併記します。
4. 実際のご相談ケース
商標の譲渡にあたり、「いくらで売るのが妥当か」「どのように根拠を示せばよいか」といったご相談をいただくことがあります。
当事務所では、その商標が使われている商品・サービスの売上や利益の概算をもとに、RFR法により評価書を作成します。評価書では、ロイヤルティ率や前提条件を整理し、算出した商標の評価額をわかりやすくまとめています。これにより、関係者が共通の前提をもって検討を進めやすくなります。
このように、商標が事業や売上にどのように関わっているかを数値で整理することで、感覚ではなく客観的な根拠に基づいた判断が可能になります。
5. 料金と納期(簡易RFR)
- 料金:税込 110,000円
- 納期:ドラフト最短 5営業日
- 範囲:前提条件・計算ステップ・条件を変えた比較(感度分析)を明示
- 守秘:弁理士の守秘義務の下、目的外利用なし(必要に応じてNDA締結可)
実際のサービス内容や料金のイメージは、商標価値の簡易評価(簡易RFRレポート)のページで詳しくご紹介しています。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 出願中でも評価できますか?
A. 可能です。登録未確定の不確実性を織り込み、保守的な前提で評価額を提示します。「登録成立を前提」などの条件を明記し、登録状況に応じた再計算にも対応します。
Q2. まだ売上がない段階はどう扱いますか?
A. 売上データがない段階では、「これからどれだけ利益が出るか」を使う通常のRFR法は使えません。そのため、まずは「もし同じ商標を一から取得するとしたら、どれくらい費用がかかるか」 といった再取得コストなどを基準に、参考的な評価額として提示します(概算のため控えめの数値になりがちです)。
Q3. 秘密保持はどうなっていますか?
A. 弁理士には守秘義務があり、原則NDA不要です。社内規程等で必要な場合はNDA締結に対応します(自社書式の持ち込み可)。
※ 本記事は一般的な解説です。個別案件では前提条件をすり合わせたうえで評価額のレンジ(評価額の幅)を提示します。
📐 計算・資料作成の手間、すべて代行します
「ロジックは理解できたが、自分で計算するのは不安」「社外へ出すため、専門家の名前が入った評価書が欲しい」という場合は、当事務所の簡易評価サービスをご活用ください。最短5営業日・11万円(税込)で、本記事で解説したRFR法に基づく評価書(PDF)を作成・納品いたします。
関連記事
商標価値評価(簡易RFR)に関する関連記事をまとめた一覧は、こちらの総合ページに整理しています:商標価値評価|RFR法の基礎と実務ガイド(まとめ)
次の一歩
- 商標価値の簡易評価サービス(簡易RFRレポート):自社ブランドの価値をざっくり数字で把握したい方向けのサービスです。
- 簡易RFRによる商標価値評価が事業判断の根拠になる理由:なぜこのRFR法が社内稟議や交渉で使えるのかという論理的根拠を深く知りたい方はこちらをご覧ください。
- 3Dプリント試作サービス:新しいブランドとあわせて製品の試作も進めたい場合はこちらをご覧ください。
- 無料相談(30分):どのサービスが自社に合うか分からない場合は、まずは無料相談で方向性を一緒に整理します。
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)