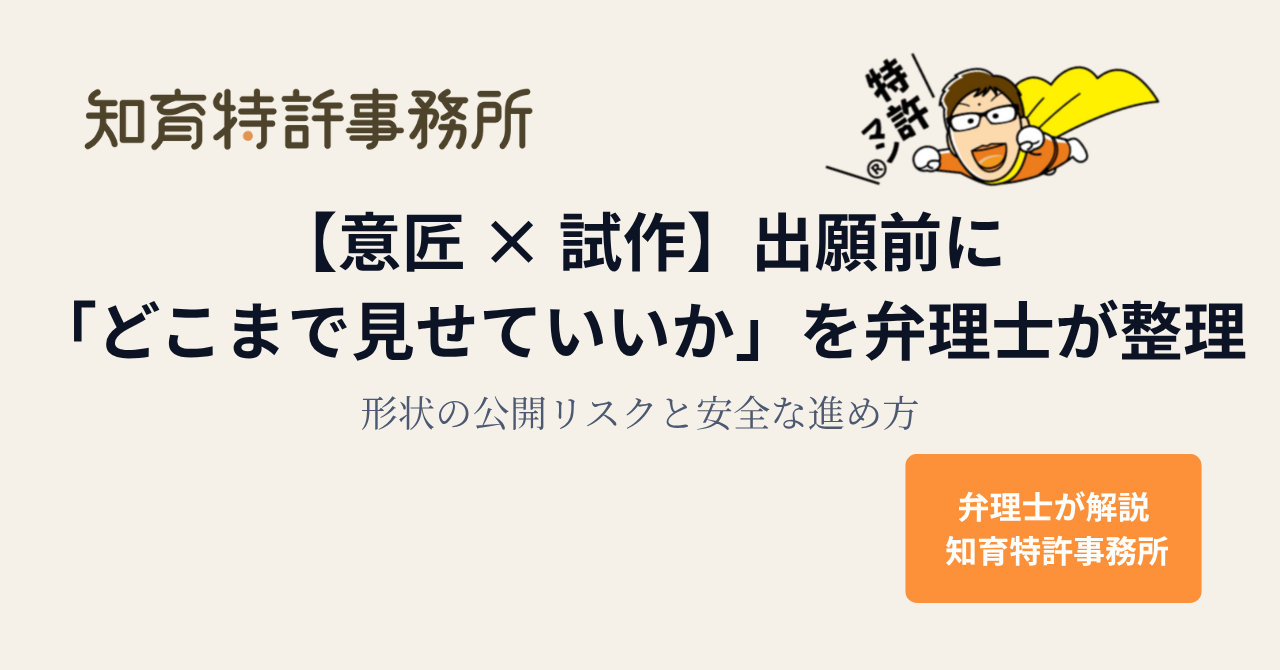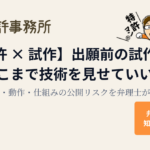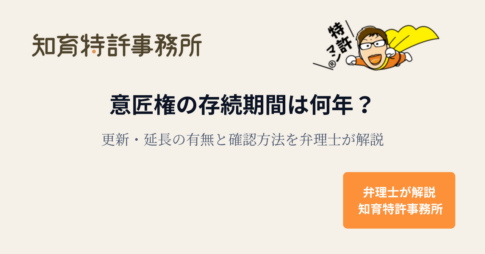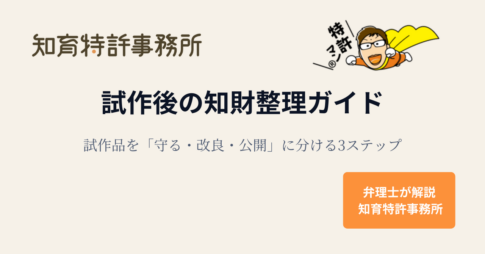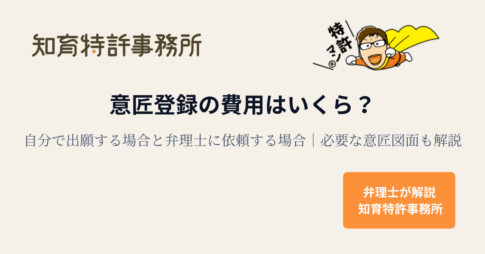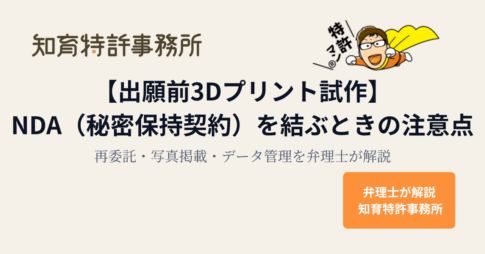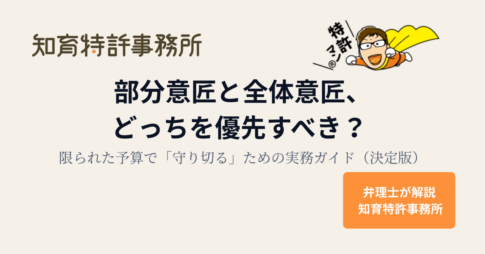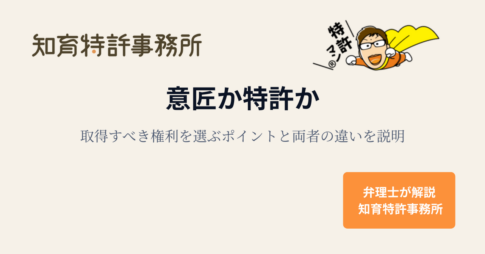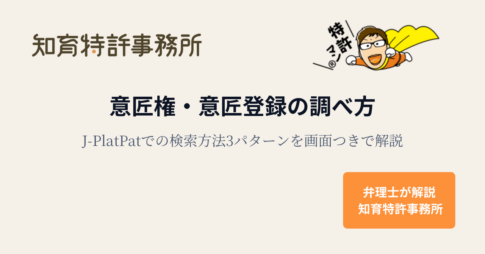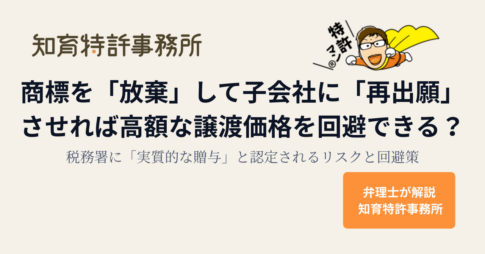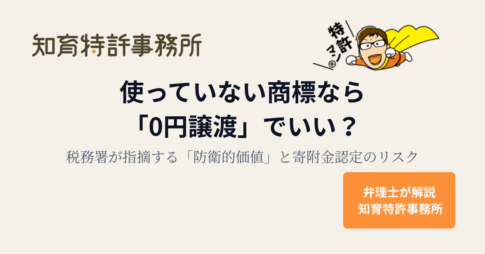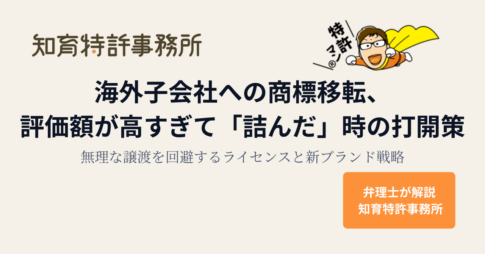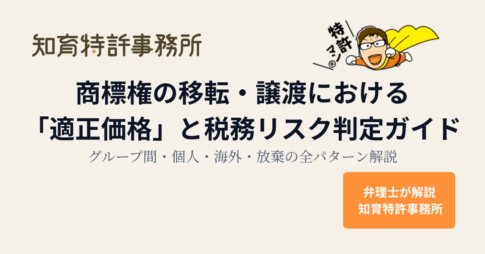製品のデザインを固める段階では、試作を作って「形状の見え方」「使い勝手」「全体のバランス」を確認する場面があります。
しかし、意匠(デザイン)を出願する予定がある場合、試作品の写真を公開したり、外部の試作会社にデータを渡す際には「デザインの特徴が他人に分かってしまう」という公開リスクが生じます。
この記事では、意匠出願を見据えたときに 試作をどこまで見せてよいのか、またどのように試作を進めれば安全かを弁理士が分かりやすく整理します。
なお、このページは出願前の「意匠 × 試作」に絞って整理しています。 特許・意匠・3Dプリント試作・商標価値評価までまとめて全体像を押さえたい方は、「知財・3Dプリント試作・商標価値評価の総合ガイド」もあわせてご覧ください。
出願前3Dプリント試作の全体像はこちら 👉 特許・意匠の出願前3D試作の総合ガイド
1. 意匠の新規性は「形の特徴がどこまで見えているか」で判断される
意匠では、製品の外観が主な保護対象になります。ここでいう「外観」とは、製品を見たときにどこが目立つか・どんな形に見えるかという、見た目そのものを指します。例えば、次のような「見てすぐ分かる部分」が外観に含まれます。
- 全体の輪郭(丸い・四角い・細長い 等)
- 目立つふくらみやへこみの形
- 特徴的な曲線・エッジのライン
- 上下・左右のバランスや厚みの印象
これらがハッキリ分かる形で試作品が公開されると、「そのような形の製品はすでに公表されている」とみなされ、意匠としての新規性が失われるおそれがあります。
2. 出願前に「見せてよい情報」と「見せると危険な情報」
意匠の新規性は、第三者が外観の「どの特徴」を認識できるかで判断されます。そのため、試作段階で公開する場合は、「特徴が分かるか/分からないか」を基準に切り分ける必要があります。
2-1. 比較的安全な公開(外観の特徴が分からない)
次のように、形の特徴がわからない状態であれば、新規性を失う可能性は小さくなることがあります。
- 遠景の写真(形状がはっきりしない)
- 手に持っているが、重要な形状が隠れている
- 影・逆光で形が認識できない
- デザインの特徴を布や指で隠している状態
ポイントは、👉「第三者が、どんな形なのか判断できないこと」。形が判別できる見せ方は新規性を失うリスクが高まります。
2-2. 危険な公開(外観の特徴がはっきり分かる)
以下のように、外観の特徴を認識できる公開は、意匠の新規性を失うおそれが高く、出願前は避けるべきです。
- 特徴部分が写った近距離の写真
- 外観の特徴が一目で分かる角度から撮影した写真
- 3D CAD画像やレンダリング画像
- 特徴的な曲線・エッジが分かる明るい写真
つまり、👉「第三者が、この製品はこういう形だな」と理解できる公開は危険と覚えておくと判断しやすくなります。
3. 完成前でも意匠出願できる|「確定した外観部分だけ」先に出願できる
意匠では、製品全体のデザインがまだ完成していなくても、「ここはもう変える予定がない」「この部分だけは確実に守りたい」という一部の外観が固まっていれば、その部分だけを先に出願できる場合があります。たとえば、次のようなケースです。
- 取っ手・ボタン・ダイヤルなど、製品の一部分としてまとまって見える部分の形だけが先に決まっている
- 正面パネルの一部や表示枠など、「ここだけはこの見た目にしたい」という外観が固まっている
- 機能上どうしても変えられない部位の形があり、その見え方だけは先に守っておきたい
- 全体の仕様や細部は調整中だが、ユーザーの目に入るメインの見せ方だけは確定している
このような「完成している範囲だけ」を先に権利化しておくために使えるのが、部分意匠(外観の一部分だけを保護する制度)です。部分意匠を使えば、試作段階でも確定している部分だけ先に守り、あとから残りのデザインを整えるという進め方が可能になります。
4. 外部試作ではNDA(秘密保持契約)が必須|意匠は形の流出が致命的
意匠出願における最大のリスクは、形の特徴が外部に伝わることです。外部試作を依頼する場合は、NDAで次の点を必ず押さえてください。
- 再委託がある場合は必ず事前に知らせてもらう
- SNSなどで実績紹介として試作品の写真を公開しない
- 試作データの保存期間と削除方法を明確にする
- 必要最小限のデータだけ渡す運用にする
👉 詳しくはこちら:出願前試作のNDAで必ず確認すべきポイント
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 製品を使用している写真は、出願前に公開しても大丈夫ですか?
判断ポイントは 写真から製品の形が分かるかどうか です。
▼ 比較的安全な例(形が分からない)
- 手の中にすっぽり隠れていて形が見えない
- ピントが合っておらず輪郭や細部が分からない
- 影や逆光で形状がわからない
- デザインの特徴部分が手や布で隠れている
▼ 危険な例(形が分かる)
- 製品の輪郭がはっきり写っている
- どんな形かわかるレベルで見えている
- 曲線・角・ふくらみ・へこみなどが判別できる
迷うときは「形が分かるかどうか」で判断します。少しでも形が分かるような写真なら公開しないのが安全です。
Q2. どういう写真の撮り方が特に危険ですか?
「その写真1枚で、どんな形か分かってしまう撮り方」これが一番危ないです。
例としては:
- 製品をまっすぐ真正面から写した写真
- 横から撮って、厚みや輪郭が分かる写真
- 上から撮って、外周の形が分かる写真
- 少し斜めから撮って、全体のシルエットが見える写真(いわゆる “斜め方向からの写真”)
つまり、他人が形を想像できてしまう写真は全部NG です。逆に、外観が分からない撮り方なら比較的安全です。
Q3. 意匠は形が流出したらもう権利が取れませんか?
形が流失しても「新規性喪失の例外」という救済ルールをつかうことで権利が取れる場合もありますが、次のようなリスクがあります:
- 救済ルールを使える期限がある
- 救済ルールを使うために証拠資料を揃える必要がある
- 救済ルールが使えないこともある
- 救済ルールを使っても競合に先に出願されてしまう場合がある
そのため、できるだけ出願前には「形が分かる写真などを公開」しない方が安心 です。
Q4. 出願前に見せてもよい範囲は?
ポイントは 第三者が形を再現できるかどうか です。
▼ 比較的安全な例(形が特定できない例)
- 遠くて形が分からない
- 影になって輪郭が見えない
- ぼかし・モザイクが入っている
- 一部を隠している
- 手で持っているが形が読み取れない
▼ 危険な例(形が特定できる例)
- シルエットがそのまま分かる
- 全体の形が想像できる
- 曲線や角の特徴が把握できる
少しでも形が分かるなら、原則として公開しないのが安全です。
6. まとめ:意匠は「形の特徴が相手に伝わるか」がすべて
出願前に試作品を見せたい場合、もっとも重要なのは「外観の特徴が第三者に伝わるかどうか」 という点です。意匠では、この一点が新規性リスクの分かれ目になります。試作段階でも、次の4つを意識するだけで公開リスクを大きく下げられます。
- 特徴が分かる見せ方を避ける(近接写真・形が分かる写真はNG)
- どうしても見せる必要がある場合は、形がわからない状態にする
- 外部試作はNDAで管理する(再委託・掲載禁止・データ削除)
- 固まっている外観部分だけ先に意匠出願する
これらを押さえておけば、試作段階でも安全にプロジェクトを進められます。
次の一歩
- 3Dプリント試作サービス:触れる試作パック/知財戦略パックの内容や料金はこちらからご覧いただけます。
- 知財・試作・商標価値評価の総合ガイド:特許・意匠・商標との関係も含めて全体像を整理したい方はこちら。
- 無料相談(30分):試作の進め方や出願タイミングでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)