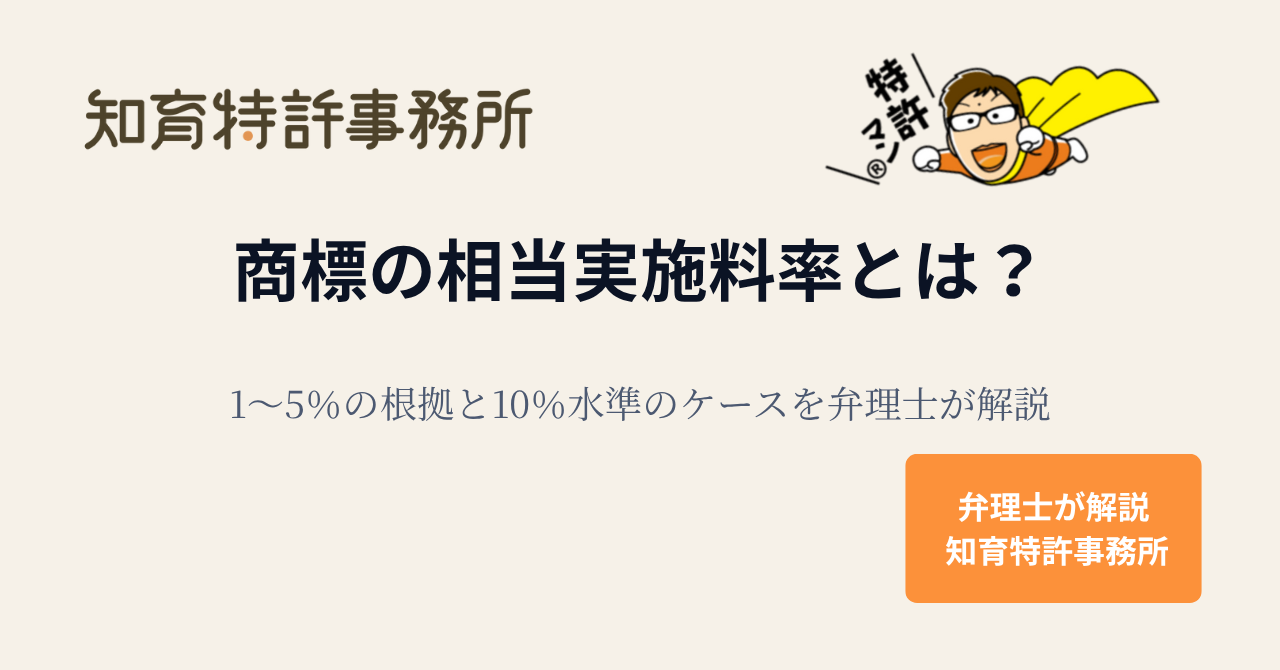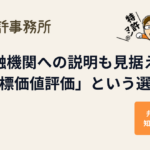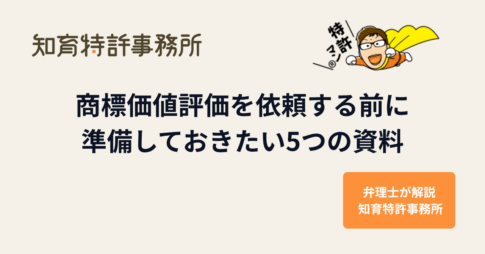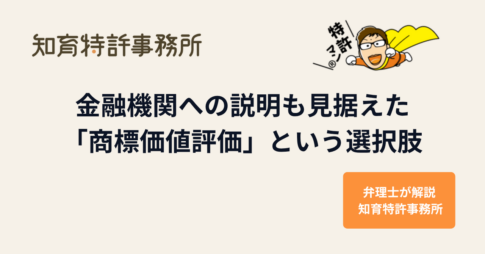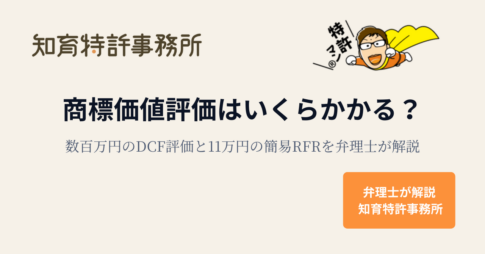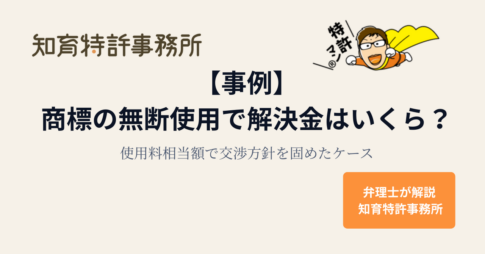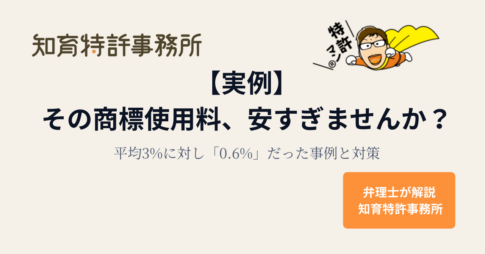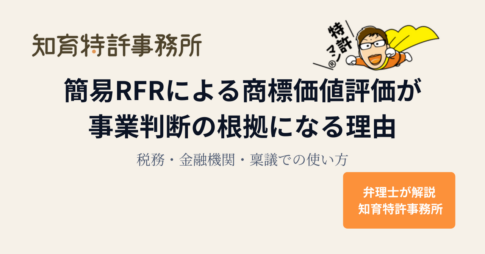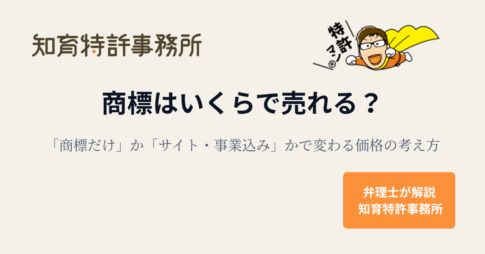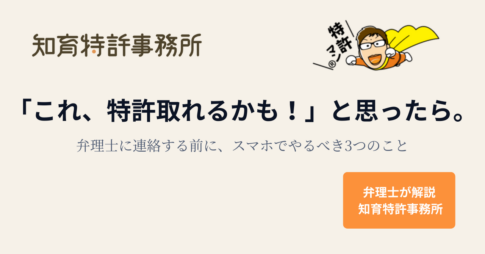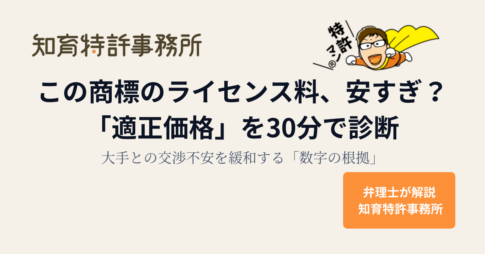商標の価値を数字で説明するとき、最初の出発点になるのが「相当実施料率(ライセンス料率)」です。
本記事では、実務でよく使われる1〜5%という料率の根拠と、10%水準が検討されるケース、そして料率を上げ下げするときの考え方を整理します。
「売上の中で“商標の貢献分(=料率)”を何%と見るか」を検討したい方向けの解説です。商標価値評価の全体の流れは、総合ガイド👉 商標価値の出し方(簡易RFR)もあわせてご覧ください。
1. 相当実施料率とは?
相当実施料率とは、「他社の商標を借りて使うとしたら、売上の何%を使用料として支払うか」という割合です。たとえば自社ブランドで年間1,000万円の売上がある場合、そのうちブランドの信用や知名度によって支えられている部分を3%と見れば、使用料は年間30万円になります。この使用料の割合(相当実施料率)が、商標の価値を考えるときの出発点になります。
料率は1つの数字に固定せず、幅(例:2〜4%)で示すのが実務的です。料率を「慎重に見た場合」「普通に見た場合」「強気に見た場合」などのように並べて比較できた方が、交渉や稟議の場において関係者が数字の妥当性を共有しやすいからです。また、料率に幅(レンジ)を設けておくと、売上などの前提が少し変わっても、評価額がおおよそどの範囲で増減するかを事前に共有できるため、評価の透明性を保ったまま、根拠のある説明がしやすくなります。
2. 「1〜5%」の料率が多い理由
1〜5%という料率の幅は、過去の裁判例や業界調査の中で商標の料率として多く出ている範囲です。ただし、商標の使われ方や事業の性格によって料率は上下します。
実務や裁判例のデータを見ると、商標のライセンス料率は1〜5%に集中している一方で、著名ブランドや特殊な事情があるケースでは、10%前後、場合によっては10〜15%や15〜20%といった高い料率が認められた例もあります。ただし、これらはあくまで少数派であり、「一般的な目安」としては1〜5%を中心に考えるのが現実的です。
下の表は、実務で料率を判断するときに使われる考え方の一例をまとめたものです。「どんなブランドなら料率が高めになるのか」「どんなケースなら料率が控えめか」を整理しています。
| 評価の傾向 | 状況の例 | 料率の目安 |
|---|---|---|
| 料率が上振れ(高め) | 商品名・サービス名として広く知られている/名前が変わると売上が下がる | 約3〜5% |
| 料率が標準 | 一般的な自社ブランドとして流通している | 約2〜3% |
| 料率が下振れ(控えめ) | 新規ブランド・使用期間が短い・広告主導で売れている | 約1〜2% |
特許との違い:特許は技術の独占が効くため、ケースによっては料率は高め(例:5〜10%など)になりやすいのに対し、商標は「識別・信用の力」が中心のため、一般的には料率が控えめ(例:1〜5%)に収まる傾向があります。もっとも、有名ブランドなど一部のケースでは10%前後の高い料率が採用される例もあり、ブランド力や交渉条件によって料率が変動する点には注意が必要です。
3. 料率を考えるときの3つの視点
商標の料率を決めるときは、「商標がどれだけ売上に貢献しているか」を整理することが大切です。売上に貢献しているかの目安として、次の3つの視点を確認します。
- 知名度と独自性:商標(ブランド名)がどれくらい認知されているか。検索・口コミ・リピート購入などが多いほど、商標による信頼や集客効果が高いと判断できます。
- 利用範囲の広さ:商標がどんな商品・サービスに使われているか。たとえば「商標の登録区分が多い」「直販・卸・ECなど販路が広い」「海外展開がある」場合、商標の影響範囲が広く、売上への寄与も大きく評価されます。
- 事業の安定性:商標が関わる商品・サービスの売上が安定しているか。返品・解約が少なく、広告を減らしても一定の売上が続くブランドは、商標そのものが事業基盤を支えていると考えられます。
これら3つの視点を整理しておくと、料率の設定が「なんとなくの感覚」ではなく、説明できる根拠に基づいたものになります。さらに、料率を1つに決め打ちするのではなく、「標準値」と「やや高め/やや控えめ」の幅(レンジ)を持たせることで、関係者が意見を出し合いやすくなり、社内稟議や交渉の判断もスムーズになります。
4. 料率設定のイメージ(例)
ここまでで「料率の考え方」と「判断の視点」を整理しました。では実際に、商標の価値がどのくらいの金額感になるのかをイメージしてみましょう。
商標の価値は、ざっくり言えば、「売上 × 相当実施料率(%)」で求めます。この「相当実施料率」とは、商標(=ブランド名)が売上にどのくらい貢献しているかを割合で表したものです。たとえば「ブランドの力で売上の3%が支えられている」と見れば、年商1,000万円の事業では約30万円/年が「商標による貢献分」という考え方になります。
このような年商1,000万円の事業で、商標が売上に貢献している料率ごとの金額感は次のようになります。
| 想定料率 | 年間の商標価値の目安 | 想定シーン |
|---|---|---|
| 2% | 約20万円 | 新しい・使用期間が短い・広告主導で売れている |
| 3%(標準) | 約30万円 | 一般的な自社ブランドとして流通している |
| 4% | 約40万円 | 商品名・サービス名として広く認知・名前を変えると売上が下がる |
💬 補足:この計算は「商標がどれだけ売上を支えているか」を金額に置き換えた目安です。評価の目的(譲渡・融資・社内資料など)に応じて前提を調整しますが、まずは最近2〜3年ほどの実績や売上傾向をもとに試算するのが一般的です。長期の予測を立てるよりも、現状を反映した数字のほうが判断材料として使いやすいからです。
5. 料率を上げ下げする目安
以下の表は、一般的に中心となる料率(たとえば3%)を基準にして、状況に応じて料率を上げる/下げる判断をするときのチェック表です。下のような観点を整理しておくと、料率の設定理由を客観的に説明しやすくなります。
| 観点 | 料率を上げるサイン | 料率を下げるサイン | 説明のポイント |
|---|---|---|---|
| ブランド名の依存度 | 名称を変えると売上が落ちる/ 指名検索・リピートが多い | 名称を変えても 売上が大きく変わらない | 「名前そのもの」が 選ばれる理由になっているか |
| 販路・展開の広さ | 直販+卸+ECなど複数販路/ 複数区分登録あり/海外展開あり | 販路が限定/区分が少ない | 商標の影響範囲が広いほど寄与度は上がる |
| 売上の安定性 | 返品・解約が少ない/ 広告を減らしても売上が残る | 返品・解約が多い/ 広告依存が強い | 商標が継続的な売上を支えているか |
| 代替可能性 | 同業他社のブランドに置き換えにくい | 他ブランドでも代替しやすい | 代替されにくいほど料率は高めに |
💬 ポイント:「標準(例:3%)」を中心に、やや控えめ(2%)〜やや高め(4%)のレンジを用意しておくと、たとえば担当者が保守的に見積る場合や、経営側が強気に判断する場合でも、それぞれの見方を数字で比較できるため、稟議や交渉の場で根拠を共有しやすくなります。
6. 評価の進め方とご相談の流れ
実際に商標価値を評価する場合は、次の情報を整理します。
- 評価対象の商標(登録/出願番号・区分)
- 関連する事業の売上や粗利の概算
- 評価の目的(譲渡/融資/社内資料など)
これらをもとに、
1枚の要約と詳細な評価書(前提・試算・比較を明記)のセットを作成します。
まずは前提整理の無料相談で、方向性を確認ください。
7. よくある質問(抜粋)
Q1. 出願中でも評価できますか?
可能です。登録未確定の不確実性を織り込んで、やや控えめの前提で提示します。必要に応じて「登録成立を前提」などの条件を明記します。
Q2. まだ売上がない段階はどう扱いますか?
売上データがない段階では、「今後どれだけ利益が出るか」を基準にする通常のRFR法は使えません。そこで、まずは「同じ商標を一から取得するとしたら、どれくらい費用がかかるか」といった再取得コストなどを手掛かりに、参考値として控えめな評価額を提示します。
Q3. 秘密保持はどうなっていますか?
弁理士には守秘義務があります。原則NDA不要ですが、社内規程等で必要な場合はNDA締結に対応します。
関連
商標価値評価(簡易RFR)に関する関連記事をまとめた一覧は、こちらの総合ページに整理しています:👉商標価値評価|RFR法の基礎と実務ガイド(まとめ)
※本記事は一般的な説明です。実際の案件では、前提条件と目的をすり合わせた上で、複数シナリオ(料率レンジ)を提示します。
次の一歩
- 商標価値の簡易評価サービス(簡易RFRレポート):自社ブランドの価値をざっくり数字で把握したい方向けのサービスです。
- 簡易RFRによる商標価値評価が事業判断の根拠になる理由:なぜこのRFR法が社内稟議や交渉で使えるのかという論理的根拠を深く知りたい方はこちらをご覧ください。
- 3Dプリント試作サービス:新しいブランドとあわせて製品の試作も進めたい場合はこちらをご覧ください。
- 無料相談(30分):どのサービスが自社に合うか分からない場合は、まずは無料相談で方向性を一緒に整理します。
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)