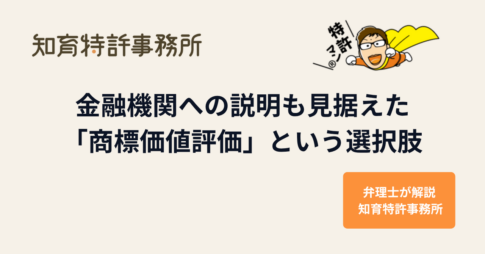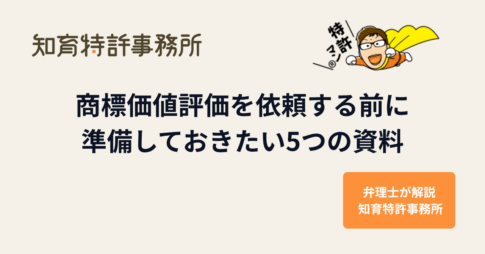「商標の価値評価を依頼したいが、相場がわからず予算が組めない」 「数百万円する鑑定と、10万円台の簡易評価、自分の目的にはどちらが必要なのか?」
商標の譲渡交渉や社内稟議を進めるにあたり、商標価値評価費用の価格帯に広さに戸惑う方も少なくありません。特に、M&Aで用いられる厳密なDCF法(数百万円)と、弊所が提供する簡易RFR法(11万円)には大きな価格差があるため、「安いほうで対外的に通用するのか?」という不安を感じる経営者や担当者の方もいるでしょう。
しかし、この価格差には明確な理由があります。それは精度の「良し悪し」ではなく、「評価の目的と前提条件」の絞り込みによるものです。 ここでは、法律面・事業面・数値面をあわせて考える弁理士の立場から、それぞれの費用の内訳と、事業目的に応じて「どこまでのコストをかけるべきか」の判断基準を解説します。
この記事を読むことで、現在の課題(交渉のたたき台が欲しい、税務上の疎明資料が必要など)に対して、高額なDCF法とリーズナブルな簡易RFR法のどちらを選ぶべきかという明確な判断軸と、簡易評価が交渉・稟議・税務上の説明に耐えうる根拠となる理由を理解できるはずです。
1. 商標価値評価における「簡易RFR法」と「本格評価(DCF法)」の違い
まず、簡易RFR法と本格評価(DCF法)の評価手法の違いから、費用の差が生まれる理由を紐解きます。計算式の細かな違いよりも、「何に時間をかけているか」という評価の工数の違いが費用の差を生みます。
1-1. 費用差を生む要因:将来予測の厳密さ
結論として、費用差の核心は 「将来予測の厳密性」 にあります。
一般的にM&Aなどで用いられる本格的なDCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)は、企業や事業が将来生み出すキャッシュフローをできる限り詳細に予測する手法です。
「今後10年の市場シェアはどうなるか?」「競合リスクは?」といった不確実な未来を予測するために、詳細な事業計画書の精査や市場調査が必要となり、公認会計士やアナリストなどの専門家チームが動くため、費用は数百万円規模になることもあります。
一方、弊所が採用している簡易RFR法(Relief from Royalty:ロイヤルティ免除法)は、長期の将来予測の前提づくりに過度な時間をかけません。 評価のベースとなるのは、「直近の売上実績」と「業界標準のロイヤルティ料率」という、すでに存在する客観的なデータです。
「この商標を第三者からライセンスして利用したとしたら、どの程度のロイヤルティを支払うのが妥当か」という観点に評価の焦点を絞り、実績値をベースに価値を算出することで、論理的整合性を保ちながら工数を大きく抑え、11万円(税込)・最短5営業日というスピード感を実現しています。
1-2. 簡易RFR評価(¥110,000)の立ち位置:最終鑑定書ではなく「交渉の出発点」
簡易RFR評価は、裁判や大規模なM&A取引で用いられるような「最終的な鑑定書」を想定したものではありません。主な役割は、交渉や社内稟議を進めるための、客観的な価格帯の目安を示すことにあります。意思決定の場面で、判断のよりどころとなる数値を短期間で用意するための道具です。
当事者同士の希望金額だけでは、議論が平行線になりやすくなります。そこで、第三者が一定の前提に基づいて算出した評価額があることで、「なぜその水準なのか」を説明しやすくなり、話し合いの土台を整えることができます。大規模M&Aの最終局面のような高い厳密性よりも、一定の合理性とスピードを重視する場面で利用することを念頭に置いた評価です。
2. 事業目的別:簡易RFRと本格評価(DCF)の最適な使い分け
商標価値評価の費用は、高ければ高いほどよいというものではありません。事業の目的や前提条件によって、求められる厳密さやスピード感が異なり、適した評価手法も変わってきます。
2-1. 簡易RFR評価が効果を発揮する利用シーン(税務・取引・判断資料)
簡易RFR評価は、特に次のような「合理的な説明」が求められる実務シーンで有効です。
- グループ会社間の権利移転(親子間・関連会社間):親会社から子会社へ商標を移転する場合などには、税務上の取り扱いに注意が必要です。無償または明らかに低すぎる価格で譲渡すると、「本来はもっと高い価格で取引すべきだった」と判断され、その差額が寄附とみなされて法人税の負担が増えるおそれがあります。簡易RFR評価は、市場で取引するとした場合のおおよその妥当な価格帯を示すことで、関連会社間取引の価格が恣意的ではないことを説明する根拠資料(疎明資料)として利用できます。
- 商標権の譲渡交渉(たたき台):売り手と買い手がそれぞれ希望価格を持っているだけでは、話し合いがまとまりにくいことがあります。簡易RFR評価に基づく価格水準を一つの目安として共有することで、双方が検討すべき価格帯が明確になり、交渉を進めやすくなります。
- 経営判断・社内稟議:ブランドの継続・見直しを検討する場面や、取締役会・経営会議での説明資料として、感覚ではなく一定の根拠を持った数字が必要になることがあります。簡易RFR評価は、「この商標を利用することで、どの程度の対価を生み出している指標」を示すため、関係者間の認識を揃えるための材料となります。
2-2. 本格評価(DCF/数百万)が必要となる主なケース
一方で、次のようなケースでは、簡易評価だけでは目的を満たせず、会計士等による本格的な評価が求められることがあります。
- 大規模なM&A(企業買収):商標だけでなく、技術、人材、顧客リストなどを含めた「企業価値(のれん)」全体を厳密に評価する必要がある場合。
- 上場(IPO)や大規模な組織再編:株主や投資家への説明責任が大きく、監査法人による詳細なチェックを前提とした評価が求められる場合。
- 訴訟・紛争:損害賠償請求などの場面で、裁判所に証拠として提出することを念頭に置いた、法的拘束力のある鑑定書が必要な場合。
このように、「交渉・税務・社内説明」レベルでの合理的な根拠が必要なのか、それとも「M&A・上場・訴訟」レベルの厳密な鑑定が必要なのかによって、選ぶべき評価方法と費用水準は変わってきます。
3. 簡易RFR評価の信頼性を裏付ける要素(客観性と守秘義務)
「費用が比較的安い=信頼性が低い」ということではありません。簡易評価であっても、専門家として一定の品質と客観性を担保するための仕組みを備えています。
3-1. 弁理士による評価の客観性と守秘義務
自社だけで評価額を試算すると、「できるだけ高く見せたい」「低く抑えたい」といった意図が入り込みやすくなります。国家資格者である弁理士が、確立された計算方法(RFR法)に基づいて評価を行うことで、評価額が「どのような前提とプロセスで金額を算定したか」を示すことができ、社内外に対しても客観性を説明しやすくなります。
また、弁理士には弁理士法第30条に基づく厳格な守秘義務が課されています。評価には「売上」「粗利」「広告宣伝費」など、経営上の重要な情報が必要となりますが、弁理士に依頼することで、これらの情報を法律上の守秘義務のもとで扱うことができます。別途NDA(秘密保持契約)を結ばなくても、法令に基づき秘密が守られる点は、法律専門職に依頼する大きな利点と言えます。
3-2. 「価格帯(幅)」で提示する透明性と実務上の利点
弊所の評価レポートでは、「〇〇円」という単一の数字ではなく、「〇〇円 〜 〇〇円」という価格帯(幅)で結果を提示することがあります。
商標権の価値は、設定するロイヤルティ料率や前提条件によって一定の幅を持ちます。あえて価格帯を提示することで、
- 前提をやや積極的に評価した場合に想定される水準
- 前提を慎重に設定した場合に想定される水準
といった形で、複数のシナリオを比較しながら検討することができます。その結果、交渉や社内稟議の場面で、「どの前提を採用するか」「どの水準を採用するか」を説明しやすくなり、意思決定のプロセスをより透明にすることにつながります。
👉 商標の相当実施料率は?1〜5%の根拠と10%水準のケースを弁理士が解説
よくある質問
Q. 簡易評価だけで銀行融資や税務調査に対応できますか?
簡易RFR評価そのものが、銀行融資における担保評価の加点として、直接用いられるケースは多くありません。一方で、事業計画の妥当性やブランドの位置づけを説明する補足資料として活用することで、金融機関との対話を整理するうえで役立つ場合があります。
税務調査においては、関連会社間取引の価格決定プロセスにおける「合理的な根拠」を示す資料として位置づけることができます。外部の専門家による評価に基づいて価格を設定していることを示すことで、恣意的な価格設定ではないことの説明に利用できます。
Q. 登録していない商標でも評価できますか?
登録前の商標であっても、評価自体は可能です。
ただし、商標としてまだ登録されていない場合は、その名前やロゴについて「自社だけが独占的に使える」という権利はまだ認められておらず、将来の審査で必ず登録になるとも限りません。このように、法的な保護や将来の登録の可否に不確実な要素が残るため、登録商標を前提とした場合と比べると、評価額も一定程度低め(ディスカウントした形)に算出するのが通常です。
そのため、登録前の評価額は、「今すぐの取引価格」というよりも、将来商標登録が完了した場合にどの程度の水準になり得るかを把握するための参考値として利用するのが現実的です。
Q. 評価に必要な資料は何ですか?
正式な決算書一式がそろっていなくても、一定の情報があれば評価を進めることは可能です。目安としては、商標が関わる商品の売上やサービス利用状況(最低限:直近数ヶ月〜1年分、望ましくは1〜3年分)など、商標と紐づく事業の実績が分かると、価値評価の前提が明確になり、精度も高めやすくなります。
- 大まかな売上金額(最低限:直近数ヶ月〜1年分でも可)
- 商標の付いた商品・サービスの売上
- 主要カテゴリごとの売上
- サービスの場合:利用件数・登録者数の推移
可能であれば、過去1〜3年分のデータがあると、売上の傾向や季節要因も踏まえて評価できるため、前提条件の検証がしやすくなります。一方で、現時点でそこまでデータが揃っていなくても、直近の数ヶ月〜1年分の情報があれば、評価をすること自体は可能です。
関連記事
次の一歩
商標価値評価で重要なのは、レポートの分量や複雑さそのものではなく、交渉・税務・社内説明などの「目的に見合った、論理的で説得力のある根拠」を持てるかどうかです。
評価の目的や活用場面を整理したうえで、どの程度の厳密さとコストのバランスを取るべきかを考えることが、適切な評価手法の選択につながります。そのためには、たとえば次のような点を整理しておくことが出発点になります。
- 何のためにこの評価が必要なのか(交渉・税務・社内説明など)
- 誰に対して説明する数字なのか(相手方企業・金融機関・社内決裁者など)
- どの程度の厳密さや検証プロセスが求められているのか
こうした整理を行ったうえで、簡易RFRで足りるのか、本格的なDCF評価まで踏み込むべきなのかを検討していくことが、適切な評価手法の選択につながります。
もし「自社の状況だとどこまでの評価が必要なのか」を判断しにくい場合は、評価の要否や進め方について、まずは短時間で方向性をすり合わせるところから始めていただくのがよいと思います。
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)