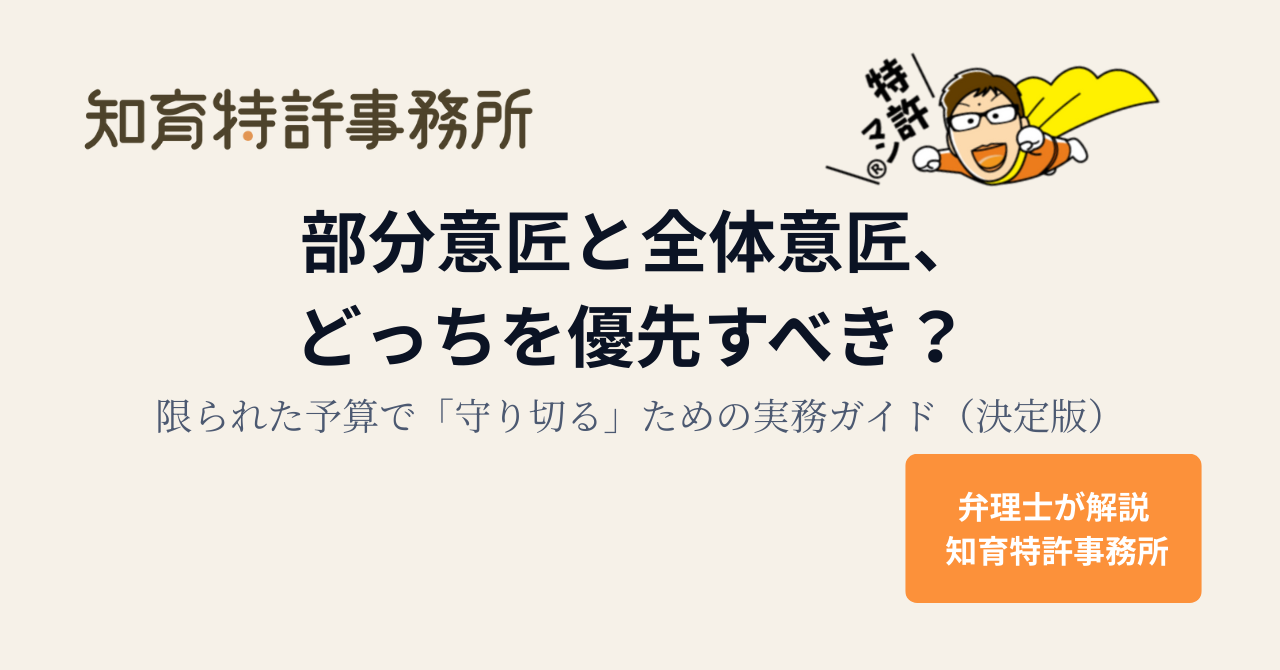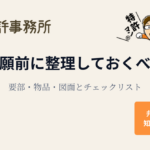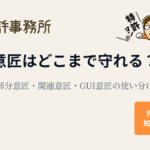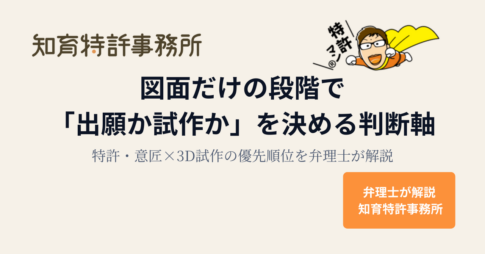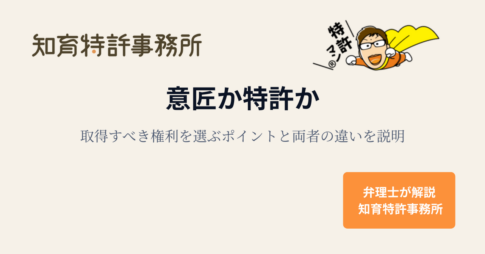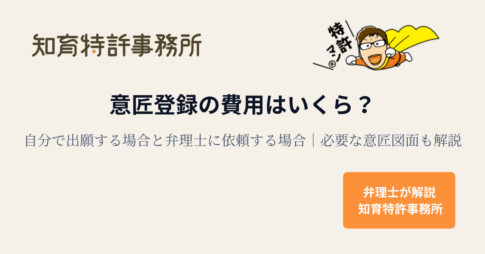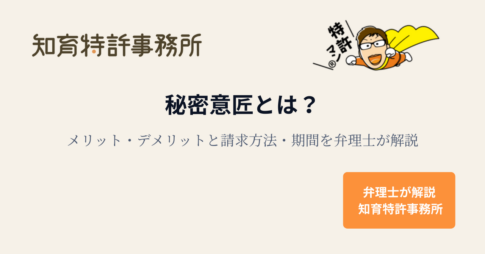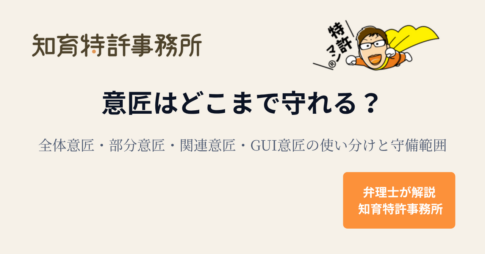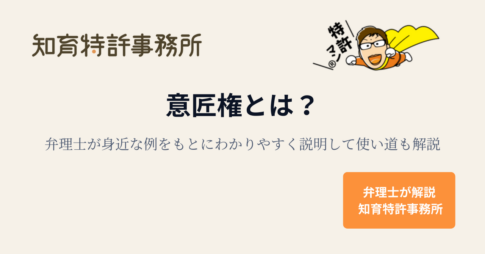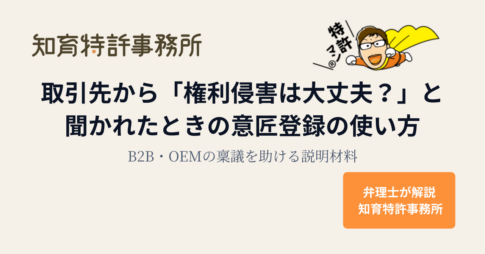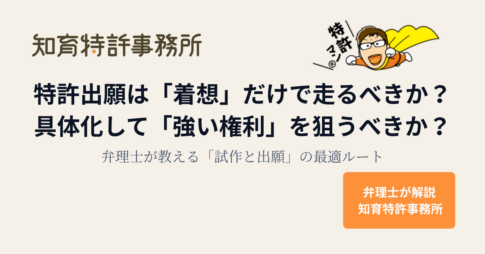意匠出願では、製品の特徴を「全体として守るか」「一部分に絞って守るか」という選択が、その後の保護範囲を大きく左右します。
コストを抑える関係で出願件数を増やせない場面では、どちらか一つを選ぶ必要がある場合もあります。
本記事では、全体意匠と部分意匠の違いが実務でどう影響するのかを、判断基準とチェックリストで整理します。
1. 全体意匠と部分意匠の「違い」が実務で影響する理由
同じデザインでも、出願形式を「全体意匠」にするか「部分意匠」にするかで、保護できる範囲は大きく変わります。
特に、模倣品の多くは製品のデザイン全体を丸ごとコピーするのではなく、特徴的な部分だけを真似してくるケースも少なくありません。このため、「全体意匠」と「部分意匠」のどちらを選ぶかによって、模倣品に対してどこまで権利を主張できるかが変わります。
また、費用の関係で出願件数を増やせない場合は、「全体意匠」と「部分意匠」のどちらか一方を選ぶことになります。
そこでまず、両者が実務上どのように違うのかを整理します。
1-1. 全体意匠と部分意匠の基本的な違い
- 全体意匠:製品全体のシルエットや外観印象をまとめて守る
- 部分意匠:製品の中でも「特徴のある部分だけ」に絞って守る
どちらを選ぶかによって、権利の及ぶ範囲、模倣品への対応、形を少し変えた将来的なモデル展開や派生製品などにも対応しやすいかどうかが変わるため、実務ではこの判断が重要になることもあります。
2. 全体意匠とは|どこまで守れる?
全体意匠は、製品全体の外観をそのまま1つの意匠として守るものです。
2-1. 全体意匠が向いているケース
- デザインの特徴が「外観全体の印象」として現れている場合
- 特徴部分を単独で切り出しても個性が伝わらず、形のまとまりで魅力が出る製品
- 各部の比率やバランス(高さ・幅・厚みなど)がデザイン性に大きく影響する製品
2-2. 全体意匠の弱点
全体意匠には、「特徴が一部分に集中している製品」に対して権利が及びにくくなる弱点があります。そのような製品では、特徴部分を少し変えるだけで「全体の外観が異なる」と判断されやすいため、 全体意匠だけでは十分にカバーできない場合があります。 (例:取っ手・ボタン・縁の形に特徴がある小型家電・工具・日用品など)
3. 部分意匠とは|「デザインの特徴部分」 をどう守る?
部分意匠は、製品全体ではなく、デザイン上の特徴が集中している一部分だけを対象にして権利化するものです。 製品の「ここが一番特徴的」という部分をピンポイントで保護できる点に特徴があります。
3-1. 部分意匠が向いているケース
- 製品を見たときに「パッと目にとまる部分」がある場合
- 製品全体の印象を大きく左右する特定のパーツがある場合
3-2. 部分意匠の強み
- 「特徴部分」だけを権利化でき、守りたいところをしっかり押さえられる
- サイズ違い・仕様違いなどのシリーズ展開があっても、特徴部分が共通していれば同じ権利を活かしやすい
- 模倣品が「特徴部分」だけを真似してくる場合でも、その箇所を直接保護できるため対処しやすい
3-3. 部分意匠の弱点
部分意匠では、製品全体の「一部分」のみが保護対象となるため、 製品全体の形や雰囲気までカバーできません。
模倣側が、製品全体の形や雰囲気はそのまま似せつつ、部分意匠で守っている「特徴部分」だけを別の形に変えてくると、
その変えられた「特徴部分」には部分意匠の権利が及びません。そのため、全体の見た目が似ていても、部分意匠だけでは製品全体のデザインを広く守ることはできません。
また、部分意匠では「どこを守る部分として示すか」がとても重要です。本当に守りたい部分以外まで保護対象に含めてしまうと、模倣側がその余計な部分を少し変えるだけで権利が及ばなくなり、結果として使いづらい権利になることがあります。
4. 判断チェックリスト|どちらを選ぶべき?
以下の3つの質問に1つでも YES があれば、部分意匠を検討する価値があります。2つ以上 YES の場合は、部分意匠の優先度が高いと言えます。
Q1. 製品を見たときに「真っ先に目につく部分」がある?
YES → 部分意匠向き
Q2. 製品全体よりも、特定のパーツが製品全体の印象を強く左右している?
YES → 部分意匠向き
Q3. 特定のパーツを少し変えるだけで、全体の印象が大きく変わる?
YES → 部分意匠向き
5. 製品ジャンル別の典型パターン
製品ジャンルごとに、デザインの特徴が現れやすい部分には一定のパターンがあります。そのため、部分意匠と全体意匠のどちらが向いているかにも共通した傾向が見られます。
ただし、以下はあくまで「よくあるパターン」であり、最終判断は製品ごとの特徴次第になります。
5-1. 容器・ボトル類
口元・キャップ・ラベル周りなど、「使うときに必ず目に入る部分」が特徴になりやすいため、部分意匠が有効なケースが多いです。
5-2. 家電・医療機器
操作部(ボタン・ダイヤル・前面パネル)や持ち手など、「使うときに必ず触れる/見る部分」が特徴になりやすい製品 が多いため、部分意匠が機能しやすい傾向があります。
5-3. 家具
- 遠目のシルエットで印象が決まる家具(椅子・テーブル) → 全体意匠が向きやすい
- 脚や取手など、一部分で個性が出る家具 → 部分意匠が機能しやすい
※脚や取手などのパーツは、単体でも1つの「製品」として扱えるため、パーツ全体の形を丸ごと意匠として押さえる方法(全体意匠)を選ぶケースもあります。
5-4. 小物・アクセサリー
角の処理・模様・ワンポイントなど小さな部分が個性になっている場合 が多く、部分意匠と相性が良いケースがあります。ただし、シルエットで魅力を出すアクセサリーは全体意匠が適する場合もあり、製品ごとの特徴に合わせた判断が必要です。
6. コストを抑える場合の考え方
出願件数を増やせない状況では、「模倣されやすい部分」を押さえることが費用対効果の面で最も合理的です。
- 模倣品は「特徴部分だけ」コピーすることが多い
- 全体意匠だけだと部分的に変えられると逃げられる
一方で、外観全体に特徴がある製品は、全体意匠で広く押さえる方法が有効です。
7. 試作段階で意識すべきこと
試作の段階は、形をまだ調整できる貴重なタイミングです。この段階で「どこが製品の特徴なのか」「どの部分は変えたくないのか」を明確にしておくと、全体意匠と部分意匠のどちらを選ぶべきかが判断しやすくなります。
- 複数の試作案を比較し、「印象を決めている部分(要部)」を特定する
- 特徴が一番出る部分がどこかを、早めに形として確認しておく
試作の時点で要部が把握できていると、出願形式の判断も迷いません。
8. よくある質問
Q1. 「全体意匠」と「部分意匠」のどちらを選べばいいですか?
製品を見たときに真っ先に目につく部分がある場合や、特定のパーツが全体の印象を左右している場合は、部分意匠を優先するのが一般的です。外観全体に特徴が広がっている製品は、全体意匠が適しています。
Q2. 全体意匠と部分意匠は両方出願した方が安全ですか?
結論として、最も安全なのは「全体意匠」と「部分意匠」をセットで出願する方法です。全体の形も、特徴部分もどちらも押さえられるため、模倣される余地が小さくなります。ただし、必ず両方が必要というわけではありません。製品の特徴がどこにあるかによって、最適な出願形式は変わります。
- 外観全体のまとまりが特徴 → 全体意匠だけで十分なケースが多い
- 特定のパーツに特徴が集中 → 部分意匠だけで十分なケースが多い
費用に限りがある場合は、まず模倣されやすい部分から押さえるのが合理的です。
Q3. 部分意匠は「部分だけ」守るものですが、全体のデザインは守れないのでしょうか?
部分意匠では、出願時に「どの部分を保護対象とするか」を図面で示す必要があり、その指定された部分だけが権利として扱われます。その他の部分は、保護範囲には含まれません。
ただし、どこまでを保護対象にするかは出願の設計次第です。ごく一部だけを保護対象から外し、残りを保護範囲として示す構成にすれば、形式が部分意匠でも、実質的に比較的広い範囲をカバーできる場合があります。
一方で、製品の特徴の出方によっては、部分意匠だけでは十分にカバーできないケースもあります。その場合は、全体の形も押さえておく意匠(全体意匠や関連意匠など)を検討することがあります。
Q4. 部分意匠の「部分」は、自分で自由に決められますか?
指定は自由ですが、示し方を誤ると本来守りたい部分が保護範囲から外れることがあります。保護範囲は、慎重に判断する必要があります。
Q5. 出願前にSNSで試作品を見せても大丈夫ですか?
原則NGです。意匠は公開すると新規性を失い、保護できなくなる可能性があります。どうしても見せる必要がある場合は、新規性喪失の例外制度を使う方法がありますが、条件や期限があるため注意が必要です。
9. まとめ
意匠出願では、製品を「全体として守るか」「特徴部分に絞って守るか」によって、権利として届く範囲が大きく変わります。
- 全体意匠は、外観の「全体の形」やまとまりがデザインの特徴となる製品に向いています。椅子・テーブル・照明器具など、ひと目見たときの形全体で印象が決まる製品では全体意匠で押さえる方法が有効です。
- 部分意匠は、製品を見たときに真っ先に目にとまる部分や特定のパーツが全体の印象を左右している製品に適しています。模倣品が「特徴部分だけ」を真似してくるケースに強く働きます。
出願件数を増やせない場合は、まず「模倣されやすい部分」を押さえる考え方が費用対効果の面で合理的です。一方で、外観全体にまとまりがあり、特徴が均等に広がっている製品は全体意匠で広く保護する方が適しています。
また、試作段階で「どこが要部なのか」「どの部分の形は変えたくないのか」を早めに確認しておくと、全体意匠と部分意匠のどちらを選ぶべきかが迷いにくくなります。
製品の特徴・ジャンル・模倣リスクを踏まえ、どちらを選ぶと最も効果的に守れるのかを見極めることが重要です。
意匠登録まわりで、あわせて読みたい記事
意匠登録の「流れ」や「守れる範囲」、「出願前の準備」など、実務の全体像をまとめて知りたい方は、こちらのページが役立ちます。
-
意匠登録まわりの記事をまとめて整理したページ(流れ・図面・試作・画面デザインなど)
└ 意匠登録の全体像と使いどころを整理したページです。 -
意匠権とは?身近な例をもとにわかりやすく説明して使い道も解説|弁理士が図解で解説
└ 「意匠権で何が守れるのか」を制度の基本から整理したい方向けの入門記事です。 -
意匠登録の流れ|図面・写真・3Dデータの実務ガイド
└ 図面・写真・3Dデータの扱いを通して、意匠登録の流れを整理したいときに役立つ記事です。 -
意匠出願前に整理しておくべきこと|要部・物品・図面とチェックリスト(弁理士解説)
└ 出願前に「どこを守るか」「物品をどう決めるか」をチェックリスト形式で確認したい方向けです。 -
【意匠 × 試作】出願前にどこまで見せていいか|デザイン公開のリスクと安全な進め方
└ 3Dプリント試作やSNS・展示会での公開について、意匠の新規性を守るための注意点を整理しています。 -
GUI意匠(画面デザイン)の基礎|アプリ・SaaSのUIを守る実務ガイド【2025年版】
└ アプリ・SaaS・機器の画面デザイン(GUI意匠)をどう守るかを整理した記事です。
次の一歩
-
意匠登録出願サポート|名古屋の弁理士が最短ルートを設計
└ 自社の状況に合わせて出願の優先順位や図面方針を相談したい方向けのサービス案内です。
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)