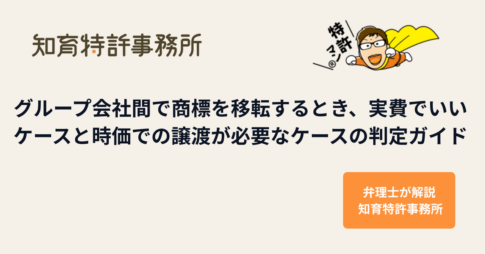「商標を身内に正規に譲渡しようとしたら、適正価格(時価)が想定以上に高くて資金的に厳しい。だったら、いったん権利を放棄して、相手側に新しく出願し直させれば、高い譲渡価格を払わずに移せるのでは?」
親会社と子会社、社長個人と自分の会社、兄弟会社同士などのように身内間で商標を譲渡する際に、高い譲渡価格をなんとか回避したいと考えたとき、「商標権の放棄→再出願」という抜け道が頭をよぎったことがある方がいるかもしれません。
しかし結論から言うと、この方法は税務署に「実質的な贈与」と認定され、多額の追徴課税を受けるリスクがあります。
この記事では、最も相談の多い親会社→子会社のケースを中心に、なぜ「商標権を放棄して再出願」でも課税されるのか、そしてどうすればリスクを回避できるのかを解説します。
なぜ「放棄して再出願」でも課税されるのか
親会社が商標権を捨てる。子会社が新しく商標出願する。一見すると、親会社と子会社の間で商標の「売買」は起きていないように見えます。
しかし、税務上は「形式」ではなく「実態」で判断されるのが原則です。
すでに売上がある商標──つまり「お金を生んでいる資産」を親会社がわざわざ捨てて、その直後にグループ内の子会社が同じ商標を取得する。税務署の目には、これは親会社が持っていた価値のある資産を、実質的に子会社へ無償で渡した」と映ります。
わかりやすくたとえるなら、「1,000万円の宝石を、親会社がわざと道端に置いて、子会社に”偶然”拾わせたようなもの」です。形式上は「落とし物」と「拾得」ですが、実態としては「渡した」のと同じです。
税務署はこうしたケースを「経済的利益の無償供与」──つまり寄附金として扱い、商標の時価との差額に対して課税してきます。
「ウチは身内だから大丈夫」が一番危ない
こうした指摘を受けやすいのは、特に身内同士の取引です。
グループ会社間、あるいは社長個人と法人の間では、「どうせ身内なんだから」「グループ全体では損得ゼロだから」と、つい価格設定が甘くなりがちです。しかし税務上は、法人格が別であれば「他人同士の取引」と同じ基準が適用されます。
こうした「グループ間であっても独立した第三者間と同様の価格(時価)で取引しなければならない」という原則については、『Q&A 知的財産権取引の国際課税・国内課税』(手塚崇史著、清文社、2010年)においても、知的財産権取引に関する基本的な税務上のルールとして解説されています。また、こうした「形式ではなく実態」で判断される具体的な事例は、『移転価格税制・海外寄附金のケーススタディ50(第2版)』(田島宏一ほか編著、中央経済社、2023年)でも詳しく取り上げられています。
この「身内間でも原則として時価での取引が必要」という考え方は、親子会社間に限った話ではありません。社長個人が自分の商標を自分の会社に移すケースでもまったく同じです。「自分の商標を自分の会社に移すだけなのに、なぜ税金がかかるのか」──この疑問については、「社長個人の商標を会社に移す時、いくらが正解?「0円・実費」の税務リスクと適正価格の算出ルール」で詳しく解説しています。
なお、国内の100%完全親子会社間(間接保有を含む完全支配関係)であれば、グループ法人税制により会社の帳簿に載っている金額(簿価)での移転が認められるケースが多いため、「放棄して再出願」のような回り道をする必要はありません。自社がどのケースに該当するかは、「グループ会社間で商標を移転するとき、実費でいいケースと時価での譲渡が必要なケースの判定ガイド」で確認できます。
商標を「放棄」すること自体は自由だが…
もちろん、商標権を放棄すること自体が常にNGなわけではありません。不要な資産を整理するのは、経営判断として当然あり得るものです。
しかし、税務上問題視されるのは、「親会社が放棄した直後に、グループ内の別法人が同じ商標を取得する」という一連の流れです。
この動きに対し、税務署は「形式」ではなく「実態」を見ます。 もし、そこに合理的な理由(その商標が本当に無価値である等)がないにもかかわらず、この一連の取引が行われた場合、「実質的には親会社から子会社へ、価値ある資産を無償で譲渡した(贈与した)」と判断され、寄附金課税の対象になるリスクが極めて高いのです。
「なんとなく」で放棄するのが最も危険──最も危険なのは、「なんとなく節税になりそうだから」という感覚だけでこの方法を実行することです。 税務調査が入った際、「なぜ譲渡ではなく放棄を選んだのか?」「なぜ直後に子会社が取得したのか?」という問いに対し、納得のいく説明をすることは現実的に極めて困難です。商標権の放棄と再出願がセットで行われている以上、どれだけ資料を用意しても「実質的な贈与」という疑いを覆すのは難しいと考えるべきでしょう。
逆に言えば、「商標権の放棄→再出願」のような回り道をせず、適正価格で譲渡手続きをする方が、結果的にリスクが低くなります。その際、「この譲渡価格が妥当である」と税務調査で説明するための根拠となるのが、専門家による商標の価値評価(評価報告書)です。
よくある質問
Q1. まだ売上がない商標でも、放棄+再出願で課税されますか?
A. まだ事業に使っていない(売上がない)商標であれば、時価はほぼ出願費用(実費)相当と評価されるのが一般的です。この場合、放棄して再出願しても、動く「価値」がほとんどないため、課税リスクは低くなります。ただし、「売上がない」という判断が正しいかどうかを裏付けるためにも、費用の明細を根拠資料として整理しておくことをお勧めします。
Q2. 評価報告書の費用と作成期間はどのくらいですか?
A. 弊所では、一律110,000円(税込)、最短5営業日で作成しています。追徴課税のリスクが数百万円〜数千万円であることを考えれば、その回避のための費用として合理的な投資です。必要な情報(売上データ等)をご提供いただければ、すぐに着手できます。
まとめ
商標をグループ内で動かすとき、「なるべくお金をかけたくない」と考えるのは経営者として当然のことです。しかし、譲渡価格を回避しようとする「抜け道」こそ、最も代償が高くつくのが税務の現実です。
安易な「商標権の放棄+再出願」は、目先の大きな支出(キャッシュアウト)こそ避けられますが、後から「見えない借金(追徴課税)」を背負うリスクと隣り合わせです。
- 「商標権の放棄+再出願」は節税の裏技ではない 👉 合理的な理由がなければ、税務署は「実質的な贈与」として課税してきます。
- 「感覚」での判断が一番危ない 👉 経営者が「ゴミ(無価値)」だと思って捨てたものが、税務署に「宝(資産)」と認定されれば、その瞬間に数百万〜数千万円の損失が確定します。
- 評価報告書は「安全なルート」を選ぶための羅針盤 👉 評価結果があれば、「価値が低いから放棄する」のか、「価値が高いからライセンスにする」のか、課税されないための正しい選択肢を事前に選べます。
追徴課税のリスクに対して、事前の調査費用(評価)はわずかな投資に過ぎません。 「お金をかけずに商標を移したい」と思ったら、自己判断で動く前に、まずは弊所の無料相談で「そもそも正規の譲渡ならいくらになるのか」を確認するところから始めてください。
※本記事に関する免責事項:本記事は、商標権の移転登録や放棄手続きに携わる弁理士の立場から、「放棄+再出願」による商標移転に伴う税務上のリスクを整理したものです。税務に関する記述は、『Q&A 知的財産権取引の国際課税・国内課税』(手塚崇史著、清文社、2010年)および『移転価格税制・海外寄附金のケーススタディ50(第2版)』(田島宏一ほか編著、中央経済社、2023年)等の公開文献に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断や税務申告上のアドバイスを行うものではありません。具体的な税務処理については、必ず税理士等の税務の専門家にご相談ください。
関連サービス
- 無料相談(オンライン・30分) 「ウチのケースでは、どの譲渡方法が安全か知りたい」という方はこちら。 👉無料相談を予約する
- 商標権の簡易価値評価サービス(一律 110,000円) 正規の譲渡における適正価格の根拠として使える評価レポートを、最短5営業日で作成します。 👉サービスの詳細・サンプルを見る
あわせて読みたい関連記事
- グループ会社間で商標を移転するとき、実費でいいケースと時価での譲渡が必要なケースの判定ガイド
└ 100%親子なら簿価でいいケースもあります。自社がどのパターンに該当するか確認できます。 - 社長個人の商標を会社に移す時、いくらが正解?「0円・実費」の税務リスクと適正価格の算出ルール
└ 社長個人⇔法人の譲渡で同じ「身内の甘え」が問題になるケースを解説しています。 - 海外子会社への商標移転、評価額が高すぎて「詰んだ」時の打開策|無理な譲渡を回避するライセンスと新ブランド戦略
└ 評価額が高額で譲渡できないケースに対する、ライセンスや新ブランドの選択肢を解説しています。 - 使っていない商標なら「0円譲渡」でいい?|税務署が指摘する「防衛的価値」と寄附金認定のリスク
└ 「使っていない=無価値」ではない理由と、未使用商標の適正な評価方法を解説しています。 - 簡易RFRによる商標価値評価が事業判断の根拠になる理由
└ 評価報告書の計算ロジックと、なぜ税務上の根拠として通用するのかを解説しています。 - 商標価値の出し方(簡易RFR)|稟議・譲渡・事業説明で使える基礎ガイド
└ RFR法による商標価値の計算方法を、具体例つきでわかりやすく解説しています。
参考文献
- 田島宏一ほか編著『移転価格税制・海外寄附金のケーススタディ50(第2版)』(中央経済社、2023年)
- 手塚崇史『Q&A 知的財産権取引の国際課税・国内課税』(清文社、2010年)
※ 寄附金課税における「実質的に贈与と認められる場合」の定義(P.20)等、基本的な法解釈の参考として引用しています。移転価格税制等の最新の運用については税理士等にご確認ください。
この記事を書いた人:弁理士・米田恵太(知育特許事務所)